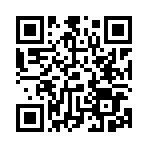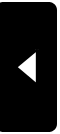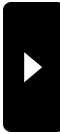2019年01月23日
1月20日(日) 東円山
東円山(481.3m)は、北海道駒ヶ岳の東側中腹に頭を出した寄生火山状のコブである。同様の峰である西円山(544m)には登山道が付けられているが、こちらにはない。鹿部町の廃棄物処理場付近から南西に延びる古い林道や陸上自衛隊演習場(飛び地)外縁の刈り払い帯、駒ヶ岳山腹の砂防用作業道などを辿って、会として初の登頂を目指した。参加は28名。
「ロイヤルホテルみなみ北海道鹿部」の駐車場に集合し、車8台で廃棄物処理場先の除雪された広場(除雪車旋回場、標高136mあたり)に到着。

リーダーから注意事項が伝えられ、8時50分に出発。脇から細枝が被る古い林道に入る。

C180m付近で体温調整を兼ねて休憩。

C250m付近はカラマツ林になっており、西方には「ゴリラ顔」の砂原岳が見え始めた。

北東方向には、噴火湾越しに室蘭方面の山々。

古い林道は木柵(雪に埋もれて頭がわずかに出ていた)に突き当たって終点となり、右手の陸上自衛隊演習場(飛び地)南縁に沿う刈り払い帯を進む。C320m付近から砂原岳と東円山のツーショット。

刈り払い帯を抜けて、C360m付近で最初の涸れ沢に沿う砂防用作業道に出ると、東円山の全容が望めた。

同じ場所から左手(南方)を望む。遠景の白い積雪地は、「函館七飯スノーパーク」から精進川を挟んで東側に広がる牧草地。暫く前まで暈(ハロ)を被っていた太陽も、低気圧の接近で厚みを増した高層雲によって、擦りガラス越しの姿になっていた。

砂原岳のゴリラ顔をアップで…。左上にプイっと頭を持ち上げた「どや顔」との評価も。

最初の涸れ沢を、作業道を利用して対岸に渡る。

二本目(最後)の涸れ沢に長い砂防ダムが設置されており、無雪期であればこの上を歩いて東円山に取り付けるが、積雪があると通過は危険と判断。右手に東円山を見ながら、上流に向かう。

涸れ沢上流部の両岸は20mほどの高さ(深さ)にえぐれ、駒ヶ岳噴火時の堆積物が明瞭な層を成している(下山時に撮影)。

上の写真の少し下流で涸れ沢を渡る。もっと下流には(砂防ダムを使わなくても)楽に渡れる地点があると思われる。


砂原岳につながる尾根のコル(440m)に到達し、東円山の頂上まで標高差40mほどを登る。


12時ちょうど、山頂に到着。三等三角点(点名:丸山)の標識を、誰かが雪面から掘り出した。ちなみに、西円山に三角点は設置されていない。

細かい雪が降り始め、砂原岳や噴火湾方面が霞んで見えなくなってきた。昼食後、恒例の全体写真を撮る。


12時30分に頂上を出発。帰路、最初の涸れ沢で見かけた風の造形「吹き溜まり」。

モノトーンの世界に彩りを添えた、ガマズミ[左]とミヤマガマズミ。
![ガマズミ[左]とミヤマガマズミ ガマズミ[左]とミヤマガマズミ](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190120-U%E6%9D%B1%E5%86%86%E5%B1%B1k%E3%82%AC%E3%83%9E%E3%82%BA%E3%83%9F%5B%E5%B7%A6%5D%E3%81%A8%E3%83%9F%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%83%9E%E3%82%BA%E3%83%9Fk.jpg)
14時30分に下山終了。帰り支度と挨拶を済ませ、車毎に現地解散した。
「ロイヤルホテルみなみ北海道鹿部」の駐車場に集合し、車8台で廃棄物処理場先の除雪された広場(除雪車旋回場、標高136mあたり)に到着。

リーダーから注意事項が伝えられ、8時50分に出発。脇から細枝が被る古い林道に入る。

C180m付近で体温調整を兼ねて休憩。

C250m付近はカラマツ林になっており、西方には「ゴリラ顔」の砂原岳が見え始めた。

北東方向には、噴火湾越しに室蘭方面の山々。

古い林道は木柵(雪に埋もれて頭がわずかに出ていた)に突き当たって終点となり、右手の陸上自衛隊演習場(飛び地)南縁に沿う刈り払い帯を進む。C320m付近から砂原岳と東円山のツーショット。

刈り払い帯を抜けて、C360m付近で最初の涸れ沢に沿う砂防用作業道に出ると、東円山の全容が望めた。

同じ場所から左手(南方)を望む。遠景の白い積雪地は、「函館七飯スノーパーク」から精進川を挟んで東側に広がる牧草地。暫く前まで暈(ハロ)を被っていた太陽も、低気圧の接近で厚みを増した高層雲によって、擦りガラス越しの姿になっていた。

砂原岳のゴリラ顔をアップで…。左上にプイっと頭を持ち上げた「どや顔」との評価も。

最初の涸れ沢を、作業道を利用して対岸に渡る。

二本目(最後)の涸れ沢に長い砂防ダムが設置されており、無雪期であればこの上を歩いて東円山に取り付けるが、積雪があると通過は危険と判断。右手に東円山を見ながら、上流に向かう。

涸れ沢上流部の両岸は20mほどの高さ(深さ)にえぐれ、駒ヶ岳噴火時の堆積物が明瞭な層を成している(下山時に撮影)。

上の写真の少し下流で涸れ沢を渡る。もっと下流には(砂防ダムを使わなくても)楽に渡れる地点があると思われる。


砂原岳につながる尾根のコル(440m)に到達し、東円山の頂上まで標高差40mほどを登る。


12時ちょうど、山頂に到着。三等三角点(点名:丸山)の標識を、誰かが雪面から掘り出した。ちなみに、西円山に三角点は設置されていない。

細かい雪が降り始め、砂原岳や噴火湾方面が霞んで見えなくなってきた。昼食後、恒例の全体写真を撮る。


12時30分に頂上を出発。帰路、最初の涸れ沢で見かけた風の造形「吹き溜まり」。

モノトーンの世界に彩りを添えた、ガマズミ[左]とミヤマガマズミ。
![ガマズミ[左]とミヤマガマズミ ガマズミ[左]とミヤマガマズミ](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190120-U%E6%9D%B1%E5%86%86%E5%B1%B1k%E3%82%AC%E3%83%9E%E3%82%BA%E3%83%9F%5B%E5%B7%A6%5D%E3%81%A8%E3%83%9F%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%83%9E%E3%82%BA%E3%83%9Fk.jpg)
14時30分に下山終了。帰り支度と挨拶を済ませ、車毎に現地解散した。
2019年01月14日
1月13日 石山
1月の自然部山行は石崎の地主海神社西方の石山。毎年登っているが,今年は積雪が少ない。天気予報は晴れだったが,神社に着いたときは雪がちらついていた。神主さんに挨拶を済ませ,10時にほとんどがツボ足で出発。

いつもの林道から尾根に取り付く。針葉樹林から広葉樹林に変わると雪もなくなった。


尾根に取り付いたところで休憩。尾根道にはまだ雪が積もっているが,十分ツボ足で歩ける。


少し林道を歩き,また尾根に取り付き,前衛320m峰に向かう。

11時前衛峰到着。しばし展望を楽しみながら休憩。天気も良くなってきた。




休憩後,石山本峰へ向かう。頂上近くになると積雪も多くなったが,まだ固まっていないのでスノーシューでもかなり沈む。


11時半,頂上着。天気も良くなり,風もないのでゆっくり昼食を摂る。


石山の岩の周りで全体写真を撮り,12時に下山開始。




前衛峰から南西斜面を下る。最後は急斜面。


13時前に下山終了。お参りをするメンバーもあり。帰り支度を済ませ,車毎に現地解散した。


いつもの林道から尾根に取り付く。針葉樹林から広葉樹林に変わると雪もなくなった。


尾根に取り付いたところで休憩。尾根道にはまだ雪が積もっているが,十分ツボ足で歩ける。


少し林道を歩き,また尾根に取り付き,前衛320m峰に向かう。

11時前衛峰到着。しばし展望を楽しみながら休憩。天気も良くなってきた。



休憩後,石山本峰へ向かう。頂上近くになると積雪も多くなったが,まだ固まっていないのでスノーシューでもかなり沈む。


11時半,頂上着。天気も良くなり,風もないのでゆっくり昼食を摂る。


石山の岩の周りで全体写真を撮り,12時に下山開始。



前衛峰から南西斜面を下る。最後は急斜面。


13時前に下山終了。お参りをするメンバーもあり。帰り支度を済ませ,車毎に現地解散した。

2019年01月08日
1月6日(日) 函館山
今年初の会山行は恒例の函館山。新年の交礼会でもあり、参加は22名だった。
函館山管理事務所の駐車場に集合。リーダーの一人は10時まで待機し、他は予定より少し早く9時50分に出発。
先ずは今年の登山の安全祈願のため、函館八幡宮へ向かう。

積雪は20cm足らずだが、積もった雪が面白い造形を見せてくれる。キャンプ施設の屋根から垂れ下がった雪。

宮の森コースの木道に被さる樹木の枝に積もった雪。

函館八幡宮に参拝。

参拝後、二組で別ルートを登る。こちらの組は尾根で休憩。雪がちらつく中、うっすらと街並みが望めた。

急斜面を進む。樹木の幹に付着した雪の模様が美しい。

まもなく上部に到着。

所用で早く下山するメンバーのため、一回目の集合写真を撮る。


雪の合間に望む御殿山と街並みは、趣がある。


別組が合流。先に下山した3人を除いて、二回目の集合写真を撮る。


ここで解散して、御殿山のロープウェイ駅に向かうグループ、下山して食事&入浴に谷地頭温泉へ向かうグループなどに分かれた。
千畳敷コース脇の樹木は、雪の花が満開。

[おまけ]旧山道コース脇の柵に積もった雪の造形。

雪がちらついたが風は弱く、時折り雲の切れ間から部分日食中の太陽が顔を出すなど、まずまずの登り初めになった。
会メンバーのブログ(こちら)もご覧ください。
本年も宜しくお願いします。
函館山管理事務所の駐車場に集合。リーダーの一人は10時まで待機し、他は予定より少し早く9時50分に出発。
先ずは今年の登山の安全祈願のため、函館八幡宮へ向かう。

積雪は20cm足らずだが、積もった雪が面白い造形を見せてくれる。キャンプ施設の屋根から垂れ下がった雪。

宮の森コースの木道に被さる樹木の枝に積もった雪。

函館八幡宮に参拝。

参拝後、二組で別ルートを登る。こちらの組は尾根で休憩。雪がちらつく中、うっすらと街並みが望めた。

急斜面を進む。樹木の幹に付着した雪の模様が美しい。

まもなく上部に到着。

所用で早く下山するメンバーのため、一回目の集合写真を撮る。


雪の合間に望む御殿山と街並みは、趣がある。


別組が合流。先に下山した3人を除いて、二回目の集合写真を撮る。


ここで解散して、御殿山のロープウェイ駅に向かうグループ、下山して食事&入浴に谷地頭温泉へ向かうグループなどに分かれた。
千畳敷コース脇の樹木は、雪の花が満開。

[おまけ]旧山道コース脇の柵に積もった雪の造形。

雪がちらついたが風は弱く、時折り雲の切れ間から部分日食中の太陽が顔を出すなど、まずまずの登り初めになった。
会メンバーのブログ(こちら)もご覧ください。
本年も宜しくお願いします。
2019年01月02日
12月30日 庄司山
今回の山行は毎年恒例の庄司山納会登山。今年は都合により30日となってしまったため,忙しくて参加できない会員も多かった。参加できなかった会員は個人的に一週間前に登ったとのこと。その時は雪もほとんどなかったということだが,30日は前日・前々日の大雪で山の積雪の状況や駐車スペースが心配された。心配した通り,いつもの駐車スペースまで行けず,かなり手前の農家の脇に駐車させてもらった。たまたまその農家の人が来ており,気持ちよく駐車させてくれた。天気予報は曇り時々雪だったが,歩き始めは快晴で山頂の展望が期待された。
9時半に出発。1.3㎞ほど畑を横断して10時過ぎに本来の駐車スペースに到着。

蒜沢川左岸のルートはまだ動物の足跡しかない雪道だったが,積雪量はそれほど多くなかった。適当にラッセルを交代しながら進む。

10時50分ころいよいよ登りに入る。

ジグザグの登り。途中で雪が降ってきた。尾根への取り付きでは風も強くなった。

尾根道を進むと風も雪も治まって来た。もう少しで頂上。

頂上到着12時。おしるこ準備組と奥の岩まで行く組,居残り組とに分かれる。


頂上の祠は少し移動してあった。

奥岩組を待つ間,各自写真を撮ったり,昼ご飯を摂ったり。展望も良くなり,函館山や下北半島も見えてきた。



奥岩組も戻り,昼食とおしるこをいただき,12時50分下山開始。その前に函館山を背景に全体写真。

下山は速い。13時40分には登山口到着。少し休んで残る畑歩きに入る。見晴らしはよいが,畑は積雪が少なく歩き難い。


14時過ぎに下山終了。Sさんが毎年用意してくれるホットコーヒーをいただく。冷えた身体に温かい飲み物が有り難い。コーヒーをいただきながら,会長・副会長の挨拶があり,その後車ごとに解散した。今年無事に登山を楽しめたように,来年も楽しく登れますように。
9時半に出発。1.3㎞ほど畑を横断して10時過ぎに本来の駐車スペースに到着。

蒜沢川左岸のルートはまだ動物の足跡しかない雪道だったが,積雪量はそれほど多くなかった。適当にラッセルを交代しながら進む。

10時50分ころいよいよ登りに入る。

ジグザグの登り。途中で雪が降ってきた。尾根への取り付きでは風も強くなった。

尾根道を進むと風も雪も治まって来た。もう少しで頂上。

頂上到着12時。おしるこ準備組と奥の岩まで行く組,居残り組とに分かれる。


頂上の祠は少し移動してあった。

奥岩組を待つ間,各自写真を撮ったり,昼ご飯を摂ったり。展望も良くなり,函館山や下北半島も見えてきた。



奥岩組も戻り,昼食とおしるこをいただき,12時50分下山開始。その前に函館山を背景に全体写真。

下山は速い。13時40分には登山口到着。少し休んで残る畑歩きに入る。見晴らしはよいが,畑は積雪が少なく歩き難い。


14時過ぎに下山終了。Sさんが毎年用意してくれるホットコーヒーをいただく。冷えた身体に温かい飲み物が有り難い。コーヒーをいただきながら,会長・副会長の挨拶があり,その後車ごとに解散した。今年無事に登山を楽しめたように,来年も楽しく登れますように。
2018年12月20日
12月16日 遊楽部川バードウォッチング
12月の自然部山行は毎年恒例の遊楽部川バードウォッチング。今年は12名の参加となった。天気予報は曇り時々雪。第1ポイントに着いたときには小雨になり,天気が崩れるのがちょっと早いかなと思ったが,第3ポイントを過ぎるあたりから青空も見え始め,車外でも暑いくらいになった。晴れたせいか,オオワシも随分飛んでくれて,楽しませてくれた。
第1ポイント:車が着いたのに気付いたのか,川のこちら側にいたオオワシが向う岸へ移動した。望遠鏡を据えたり,双眼鏡を構えてしばし観察。


第2ポイント(建岩橋):ここで白鳥が見られたのは初めて。他にカモ類・カワアイサなど。


第3ポイント(上遊楽橋)と第4ポイントは空振りだった。
第5ポイント:家族連れや大きなカメラで狙っている人もいた。下流にオオワシやオジロワシが水遊びをしていた。写真は撮れず。
第6ポイント(セイヨウベツ橋):停車する場所がないのでゆっくり走りながら上流を見ると,同じ木に10羽くらいのオジロワシ?の群れが留まっていた。ここも写真は撮れず。
第7ポイント(大富橋):この橋の西北西方面に2つの丸山(右233m,左228m)が見えたが,その上をオオワシが群れを成して旋回しているのが見えた。そのなかからあるいは一羽で,あるいは2・3羽でこちら側の山の尾根をかすめて東へと移動して行くのが何度も見られた。その時は青空も見え,天気のいいときは鳥も随分飛ぶものかと思われた。オオワシがこれほど飛んでいるのを見たのは初めてだ。

第8ポイント(河口):カンムリカイツブリ1羽,白カモメ2羽など。海の向こうに雪を頂く駒ヶ岳がくっきり見られた。

昼食はいつも通り八雲ハーベスターだったが,日曜はバイキングのみのようで,やや高かった(大人2200円,70歳以上のシニア1650円,制限時間90分)が色々食べることができた。飲み物に紅茶とハーブティー合わせて6・7種類あり,自分でサーバーに入れて飲めるのもなかなか良かった。13時半に食事を済ませ,店頭のクリスマスリースの前で全体写真を撮って解散した。

第1ポイント:車が着いたのに気付いたのか,川のこちら側にいたオオワシが向う岸へ移動した。望遠鏡を据えたり,双眼鏡を構えてしばし観察。


第2ポイント(建岩橋):ここで白鳥が見られたのは初めて。他にカモ類・カワアイサなど。


第3ポイント(上遊楽橋)と第4ポイントは空振りだった。
第5ポイント:家族連れや大きなカメラで狙っている人もいた。下流にオオワシやオジロワシが水遊びをしていた。写真は撮れず。
第6ポイント(セイヨウベツ橋):停車する場所がないのでゆっくり走りながら上流を見ると,同じ木に10羽くらいのオジロワシ?の群れが留まっていた。ここも写真は撮れず。
第7ポイント(大富橋):この橋の西北西方面に2つの丸山(右233m,左228m)が見えたが,その上をオオワシが群れを成して旋回しているのが見えた。そのなかからあるいは一羽で,あるいは2・3羽でこちら側の山の尾根をかすめて東へと移動して行くのが何度も見られた。その時は青空も見え,天気のいいときは鳥も随分飛ぶものかと思われた。オオワシがこれほど飛んでいるのを見たのは初めてだ。

第8ポイント(河口):カンムリカイツブリ1羽,白カモメ2羽など。海の向こうに雪を頂く駒ヶ岳がくっきり見られた。

昼食はいつも通り八雲ハーベスターだったが,日曜はバイキングのみのようで,やや高かった(大人2200円,70歳以上のシニア1650円,制限時間90分)が色々食べることができた。飲み物に紅茶とハーブティー合わせて6・7種類あり,自分でサーバーに入れて飲めるのもなかなか良かった。13時半に食事を済ませ,店頭のクリスマスリースの前で全体写真を撮って解散した。