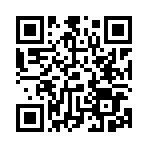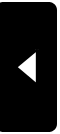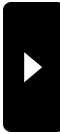2019年02月26日
2月24日 焼木尻岳
2月最後の山行は2年振りの焼木尻岳。2年前は3月19日に行っている。一か月ほど早いが雪の量と質はさほど変わらない。前回の模様はこちらをご覧ください。天気は晴れ。登るにつれて風が強くなったが,少し下りると穏やかに春めいた日差しの中の登山となった。総勢32名。
9時出発。しばらく林道を歩く。

30分ほど歩いて最初の休憩。

9時40分尾根への取り付き。


隣の下りの尾根が木立の向うに見える。

途中,無数に枝を張った「千手ブナ」が見られた。

10時半過ぎ,頂上への急登に差し掛かる。

10時46分,もう少しで頂上。

11時頂上着。しばらく展望を楽しんでから全体写真を撮った。一枚目は中二股岳(左)・二股岳(右)・駒ヶ岳(中奥)方面,二枚目は乙部岳(中)・鍋岳(やや右)方面,三枚目は北斗毛無山(左)・雷電山(右)・北斗700m峰(中奥)方面。




双耳峰の北ピークへと向かう。北ピークには雪崩の跡も見える。

北ピークから本峰を振り返る。巨大な雪庇は例年通り。

北ピークから下りのルートを10分ほど下りて貸し切りの「雪上レストラン」で昼食。ここはいつも風がなく穏やかで気持ちが良いが,羆の痕跡がいつも見られる。この日は擦りつけられた毛のような細長い物体の残る枝が落ちていた。ただし、事後のTtさん調べによると、きのこの菌糸が束になって発達した「山姥の髪の毛」と判明した。

12時下山開始。人影のなくなった「レストラン」を振り返る。

下山途中には春を感じさせるキタコブシの冬芽がたくさん見られた。

13時下山終了。挨拶の後,帰り支度を済ませ,車毎に解散した。
9時出発。しばらく林道を歩く。

30分ほど歩いて最初の休憩。

9時40分尾根への取り付き。


隣の下りの尾根が木立の向うに見える。

途中,無数に枝を張った「千手ブナ」が見られた。

10時半過ぎ,頂上への急登に差し掛かる。

10時46分,もう少しで頂上。

11時頂上着。しばらく展望を楽しんでから全体写真を撮った。一枚目は中二股岳(左)・二股岳(右)・駒ヶ岳(中奥)方面,二枚目は乙部岳(中)・鍋岳(やや右)方面,三枚目は北斗毛無山(左)・雷電山(右)・北斗700m峰(中奥)方面。




双耳峰の北ピークへと向かう。北ピークには雪崩の跡も見える。

北ピークから本峰を振り返る。巨大な雪庇は例年通り。

北ピークから下りのルートを10分ほど下りて貸し切りの「雪上レストラン」で昼食。ここはいつも風がなく穏やかで気持ちが良いが,羆の痕跡がいつも見られる。この日は擦りつけられた毛のような細長い物体の残る枝が落ちていた。ただし、事後のTtさん調べによると、きのこの菌糸が束になって発達した「山姥の髪の毛」と判明した。

12時下山開始。人影のなくなった「レストラン」を振り返る。

下山途中には春を感じさせるキタコブシの冬芽がたくさん見られた。

13時下山終了。挨拶の後,帰り支度を済ませ,車毎に解散した。
2019年02月19日
2月17日(日) 古部丸山
古部丸山(691.0m)は低山ながら、北海道で最初に設けられた一等三角点(点名「古部岳」)を持ち、三角形の端正な山容と360度の雄大な展望を誇っている。登山道は無いが、積雪期は国道278号線から函館市(旧椴法華村)絵紙山町(えがみやまちょう)の奥に延びる林道に車を乗り入れ、徒歩で林道と尾根筋を辿って登頂できる。今回の参加は16名。
【プロローグ】
集合場所の道の駅「なとわ・えさん」に向かって旧南茅部町の海岸道を走行中、朝日が昇ってきた。曙光に煌めく海面と、右手には目指す古部丸山の容姿。
![曙光と古部丸山[右] 曙光と古部丸山[右]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190217-A%E5%8F%A4%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E6%9B%99%E5%85%89%E3%81%A8%E5%8F%A4%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k.jpg)
旧椴法華村の海岸からは、朝日による美しい光芒(いわゆる「天使の梯子」)が見えた。

【さて、本題】
国道278号線から絵紙山町の林道C150あたりまで車高の高い車4台を乗り入れ、スコップで除雪して駐車スペースを確保した。準備を整え、08時35分に出発。

矢尻川支流に沿って延びる林道を辿る。正面に古部丸山の前山(596m)が見えてきた。

谷の中の林道は風が弱いので、陽が射すと春を感じられる。

林道はC283地点で沢を渡る(橋は崩落)。すぐ上流で沢は二股になっており、これまでは中央の尾根を登っていた。しかし、この上部(前山の手前)はツツジが繁茂していて、その藪漕ぎが煩わしく、枝を折ってしまうのも気が引けた。今回は、Kさんから教わった東側(上部に向かって右側)の尾根を登り、C451付近から前山に向かうルートを採った。尾根上のC380あたりにある岩峰は、左側を巻いて進む。

C451付近で、先ほどまで辿ったのと同じ林道に再び出合う。緩いコルで休憩してから、前山まで標高差150mほどの登りにかかる。

藪は余りうるさくないが、急傾斜で雪面が柔らかいため登りにくい。

傾斜がゆるくなると、正面に前山と古部丸山、左後方に恵山(617.6m)と海向山(569.4m)が望めた。


前山を乗越して、本峰に向かう。当パーティに先行して中央尾根を辿った二人組のトレースも見える(彼らとはコルで行き交った)。

最後は、標高差120m余りの登り。

強風で巻き上がる雪煙の向こうに、仲間が吸い込まれていく。11時50分、頂上に到着。

頂上には三角点の杭の傍に、新しい標識が付けられていた。

見通しは余り良くなかったが、先ず西方の景観からどうぞ。右側手前に双耳の582m峰(左)と578.0m峰。遠方やや左側に毛無山(630.6m)。
![頂上から西方[遠く毛無山] 頂上から西方[遠く毛無山]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190217-O%E5%8F%A4%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A5%BF%E6%96%B9%5B%E9%81%A0%E3%81%8F%E6%AF%9B%E7%84%A1%E5%B1%B1582m578m%5Dk.jpg)
次に南西方向。中央のどっしりした山は三枚岳(585.6m)。その左の白い山は、伐採された510m峰。右遠方は前出の毛無山。
![頂上から南西[遠く三枚岳] 頂上から南西[遠く三枚岳]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190217-P%E5%8F%A4%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8D%97%E8%A5%BF%5B%E9%81%A0%E3%81%8F%E4%B8%89%E6%9E%9A%E5%B2%B3%5Dk.jpg)
南方には、手前に572.1m峰、その向こうに津軽海峡。
![頂上から南方[手前に572.1m峰] 頂上から南方[手前に572.1m峰]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190217-Q%E5%8F%A4%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8D%97%E6%96%B9%5B%E6%89%8B%E5%89%8D%E3%81%AB572.1m%E5%B3%B0%5Dk.jpg)
そして、南東方向に恵山と海向山。
![頂上から南東[恵山&海向山] 頂上から南東[恵山&海向山]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190217-R%E5%8F%A4%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8D%97%E6%9D%B1%5B%E6%81%B5%E5%B1%B1k%E6%B5%B7%E5%90%91%E5%B1%B1%5Dk.jpg)
強風が吹き抜けて寒い頂上には5分ほど滞在しただけで11時55分、早々に下る。50mほど下がった風陰で、恵山を背景に全体写真を撮る。


直下のコルで恵山を眺めながら昼食(12時15分~40分)、同じコースを辿って下山した。C230あたりの植林地で見かけた、鹿の角研ぎ痕。

14時15分、林道終点に到着し、下山終了。除雪した駐車場所から車を出すのに苦労したが、無事に道の駅「なとわ・えさん」まで移動して解散した。
【エピローグ】
帰路、旧南茅部町古部地区の獅子鼻覆道北側入り口の横に落ちる、凍結した「白糸の滝」を見物した。

【プロローグ】
集合場所の道の駅「なとわ・えさん」に向かって旧南茅部町の海岸道を走行中、朝日が昇ってきた。曙光に煌めく海面と、右手には目指す古部丸山の容姿。
![曙光と古部丸山[右] 曙光と古部丸山[右]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190217-A%E5%8F%A4%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E6%9B%99%E5%85%89%E3%81%A8%E5%8F%A4%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k.jpg)
旧椴法華村の海岸からは、朝日による美しい光芒(いわゆる「天使の梯子」)が見えた。

【さて、本題】
国道278号線から絵紙山町の林道C150あたりまで車高の高い車4台を乗り入れ、スコップで除雪して駐車スペースを確保した。準備を整え、08時35分に出発。

矢尻川支流に沿って延びる林道を辿る。正面に古部丸山の前山(596m)が見えてきた。

谷の中の林道は風が弱いので、陽が射すと春を感じられる。

林道はC283地点で沢を渡る(橋は崩落)。すぐ上流で沢は二股になっており、これまでは中央の尾根を登っていた。しかし、この上部(前山の手前)はツツジが繁茂していて、その藪漕ぎが煩わしく、枝を折ってしまうのも気が引けた。今回は、Kさんから教わった東側(上部に向かって右側)の尾根を登り、C451付近から前山に向かうルートを採った。尾根上のC380あたりにある岩峰は、左側を巻いて進む。

C451付近で、先ほどまで辿ったのと同じ林道に再び出合う。緩いコルで休憩してから、前山まで標高差150mほどの登りにかかる。

藪は余りうるさくないが、急傾斜で雪面が柔らかいため登りにくい。

傾斜がゆるくなると、正面に前山と古部丸山、左後方に恵山(617.6m)と海向山(569.4m)が望めた。


前山を乗越して、本峰に向かう。当パーティに先行して中央尾根を辿った二人組のトレースも見える(彼らとはコルで行き交った)。

最後は、標高差120m余りの登り。

強風で巻き上がる雪煙の向こうに、仲間が吸い込まれていく。11時50分、頂上に到着。

頂上には三角点の杭の傍に、新しい標識が付けられていた。

見通しは余り良くなかったが、先ず西方の景観からどうぞ。右側手前に双耳の582m峰(左)と578.0m峰。遠方やや左側に毛無山(630.6m)。
![頂上から西方[遠く毛無山] 頂上から西方[遠く毛無山]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190217-O%E5%8F%A4%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A5%BF%E6%96%B9%5B%E9%81%A0%E3%81%8F%E6%AF%9B%E7%84%A1%E5%B1%B1582m578m%5Dk.jpg)
次に南西方向。中央のどっしりした山は三枚岳(585.6m)。その左の白い山は、伐採された510m峰。右遠方は前出の毛無山。
![頂上から南西[遠く三枚岳] 頂上から南西[遠く三枚岳]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190217-P%E5%8F%A4%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8D%97%E8%A5%BF%5B%E9%81%A0%E3%81%8F%E4%B8%89%E6%9E%9A%E5%B2%B3%5Dk.jpg)
南方には、手前に572.1m峰、その向こうに津軽海峡。
![頂上から南方[手前に572.1m峰] 頂上から南方[手前に572.1m峰]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190217-Q%E5%8F%A4%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8D%97%E6%96%B9%5B%E6%89%8B%E5%89%8D%E3%81%AB572.1m%E5%B3%B0%5Dk.jpg)
そして、南東方向に恵山と海向山。
![頂上から南東[恵山&海向山] 頂上から南東[恵山&海向山]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190217-R%E5%8F%A4%E9%83%A8%E4%B8%B8%E5%B1%B1k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E3%81%8B%E3%82%89%E5%8D%97%E6%9D%B1%5B%E6%81%B5%E5%B1%B1k%E6%B5%B7%E5%90%91%E5%B1%B1%5Dk.jpg)
強風が吹き抜けて寒い頂上には5分ほど滞在しただけで11時55分、早々に下る。50mほど下がった風陰で、恵山を背景に全体写真を撮る。


直下のコルで恵山を眺めながら昼食(12時15分~40分)、同じコースを辿って下山した。C230あたりの植林地で見かけた、鹿の角研ぎ痕。

14時15分、林道終点に到着し、下山終了。除雪した駐車場所から車を出すのに苦労したが、無事に道の駅「なとわ・えさん」まで移動して解散した。
【エピローグ】
帰路、旧南茅部町古部地区の獅子鼻覆道北側入り口の横に落ちる、凍結した「白糸の滝」を見物した。

2019年02月16日
2月14日 吉野山
2月の自然部山行は吉野山。厳しい寒さが続く中,天気は晴れたが放射冷却で冷え込んだ。登山口は南北の尾根の西側になるので日が差さず寒さが増す。9時20分出発。

林道を登って行くと少し陽が差してくる。

尾根に出たC320付近で休憩。


途中見掛けたミズナラの巨木。

頂上も間近のところにあるブナの巨木で一休み。みなさん巨木を見ながら,Tさんの雌雄同株・雌雄異株・雌雄同花などの話を聞く。



同じところで全体写真を撮る。



10時40分頂上着。少し早いが昼食にする。テーブルで優雅に食べるのはWさん。

下りは今回は尻滑りはせず,登って来たルートを下りたが,期せずして尻滑りをした人も2・3人。登りには気づかなかったキタコブシの冬芽や鹿が角をこすりつけた痕(多分)などが見られた。


12時過ぎに下山終了。朝よりも駒ヶ岳がきれいに見えた。大沼駅まで戻ってから車毎に解散した。

林道を登って行くと少し陽が差してくる。

尾根に出たC320付近で休憩。

途中見掛けたミズナラの巨木。

頂上も間近のところにあるブナの巨木で一休み。みなさん巨木を見ながら,Tさんの雌雄同株・雌雄異株・雌雄同花などの話を聞く。



同じところで全体写真を撮る。


10時40分頂上着。少し早いが昼食にする。テーブルで優雅に食べるのはWさん。

下りは今回は尻滑りはせず,登って来たルートを下りたが,期せずして尻滑りをした人も2・3人。登りには気づかなかったキタコブシの冬芽や鹿が角をこすりつけた痕(多分)などが見られた。
12時過ぎに下山終了。朝よりも駒ヶ岳がきれいに見えた。大沼駅まで戻ってから車毎に解散した。

2019年02月15日
2月6日(水) 2月例会

昨年の3月の例会は、まれにみる大雪であちらこちらで車が埋まり、めったにないことに中止となった。今年は雪ではないが、またまた、まれにみる寒波が襲ってきそう。地球温暖化からくる異常気象なのでしょうか?いつものように当たり前にやってくる春が待ち遠しい・・・・
12月と1月の行事報告
遊楽部川バードウオッチング・・・・・・例年今の時期に行われているが、オオワシがこれほど飛んでいるのを見たのは今回が初めてだった。晴れていたのが良かったのか?タイミングでいつでも見られるわけではないので今回はラッキーだった。
庄司山・・・・・・昨年は40名の参加で記録更新したが、今年は日にちの選定のせいか参加者が少なかった。恒例の山頂でのお汁粉にほっと一息。
函館山・・・・・・年中、花や野鳥そして眺望を手軽に楽しめる山。八幡宮参拝の後、2グループに分かれて登山開始。途中2か所で工事をしており、宮の森コースは木道の整備なのか3月20日ころまで通ることができず、牛の背コースも通れるが工事をしていた。
石山・・・・・・例年より雪が少なく十分ツボ足で歩けた。
東円山・・・・・・会として初めて計画された山。長い林道歩きと、途中の難所を超えると、そのまま見晴らしの良い頂上へ到着。予想より時間がかかってしまい、まさしく行ってみないとわからない山だった。
吹上山・・・・・・緩いアップダウンの長い林道が続き、侮れない山だった。山頂にサラサドウダンの立派な林があり、Tさんによると「恵山・三森山より北にサラサドウダンがあるとは思っていなかった。」とのこと。
2月の行事予定
吉野山 古部丸山 焼木尻山
学習会
山の選び方➡どこの山へ?いつ? 北海道には9個の百名山がある。その中で函館あたりから日帰りで行ける唯一の山が羊蹄山。羊蹄山を登ることができれば、他の山へどのような形で(日帰りか、山小屋泊か、テントを背負えるか?)行くことができるか計画する目安となる。花を見たいなら、北海道には8個の花の百名山がある。時期の選定はツアーのパンフレットや山の写真の撮影日などが参考になるかも。
2019年01月28日
1月27日(日) 吹上山
旧・南茅部町(現・函館市)大船温泉上の湯「ひろめ荘」の奥に鎮座する、吹上石(ぬけいし、標高500m余り)と吹上山(ふきあげやま、標高516.6m)を訪れた。吹上石は、丸いピーク上に頭を出している岩塊で、「大地の力が感じられる場所」として知られる。吹上山の頂きは灌木に覆われているが、展望は割合に良い。参加は29名。
「ひろめ荘」から500mほど奥の環境保全林ロッジ付近に集合し、スノーシューやワカンを装着して9時30分に出発。吹上石の尾根取り付き地点まで、林道を3.5kmほど辿る。15分歩いて、衣服調整のため休憩。

林道は、ほぼ北から南に向って付けられている。西(進行方向の右手)から吹き付ける強風の影響で、深雪部とクラスト部がミックスしており、先頭グループは歩きづらい。

短めの時間で先頭を交替しながら進む。

樹間から噴火湾を望む。対岸の室蘭方面は良く見えない。

C400mに近づくと、吹き溜まりが目立つようになってきた。

尾根上の457mポコを回り込んだ小さな鞍部付近には、右手の斜面を吹き上がった強風で大きな吹き溜まりの壁ができていた。

林道が丁字状に分かれる地点(C460m)に到着。吹上石に至る尾根に取り付く前に休憩をとる。木の枝の向こうは、函館市最高峰の袴腰岳(1,108.4m)方面。

尾根に上がって400mほど進むと、二つ目のピーク上に吹上石がある。五つほどある岩のうち、大きいものは10m位の高さがある。

近くの樹木に「吹上石(ぬけいし)」の標識が付けてあった。

岩塔を背にして全体写真を撮る。雪が積もった奥のテーブル状の岩に3人登っている…いわく「石の上にも三人」。

ここから東に向きを変え、350mほど離れた吹上山に向かう。いったん鞍部に下りて標高差30mほどを登るが、灌木が多くて歩きづらい。

12時25分、吹上山に到着。ここにも標識「吹上山(ふきあげやま)516.6」があった。

南東方向に、雪の模様が特徴的な三角峰・古部丸山(691.0m、北海道最初の一等三角点)。

ランチ後、2回目の全体写真を撮る。13時、帰路に付く。

吹上石に寄らず、古い林道を利用して丁字状分岐に降り立つ。

下山途中の林道から仰ぐ泣面山(奥、834.9m)は、なかなか迫力がある。左の平坦地は「万畳敷原野」。

14時40分に下山終了。帰り支度と挨拶を済ませ、温泉入浴は車毎として現地解散した。
「ひろめ荘」から500mほど奥の環境保全林ロッジ付近に集合し、スノーシューやワカンを装着して9時30分に出発。吹上石の尾根取り付き地点まで、林道を3.5kmほど辿る。15分歩いて、衣服調整のため休憩。

林道は、ほぼ北から南に向って付けられている。西(進行方向の右手)から吹き付ける強風の影響で、深雪部とクラスト部がミックスしており、先頭グループは歩きづらい。

短めの時間で先頭を交替しながら進む。

樹間から噴火湾を望む。対岸の室蘭方面は良く見えない。

C400mに近づくと、吹き溜まりが目立つようになってきた。

尾根上の457mポコを回り込んだ小さな鞍部付近には、右手の斜面を吹き上がった強風で大きな吹き溜まりの壁ができていた。

林道が丁字状に分かれる地点(C460m)に到着。吹上石に至る尾根に取り付く前に休憩をとる。木の枝の向こうは、函館市最高峰の袴腰岳(1,108.4m)方面。

尾根に上がって400mほど進むと、二つ目のピーク上に吹上石がある。五つほどある岩のうち、大きいものは10m位の高さがある。

近くの樹木に「吹上石(ぬけいし)」の標識が付けてあった。

岩塔を背にして全体写真を撮る。雪が積もった奥のテーブル状の岩に3人登っている…いわく「石の上にも三人」。

ここから東に向きを変え、350mほど離れた吹上山に向かう。いったん鞍部に下りて標高差30mほどを登るが、灌木が多くて歩きづらい。

12時25分、吹上山に到着。ここにも標識「吹上山(ふきあげやま)516.6」があった。

南東方向に、雪の模様が特徴的な三角峰・古部丸山(691.0m、北海道最初の一等三角点)。

ランチ後、2回目の全体写真を撮る。13時、帰路に付く。

吹上石に寄らず、古い林道を利用して丁字状分岐に降り立つ。

下山途中の林道から仰ぐ泣面山(奥、834.9m)は、なかなか迫力がある。左の平坦地は「万畳敷原野」。

14時40分に下山終了。帰り支度と挨拶を済ませ、温泉入浴は車毎として現地解散した。