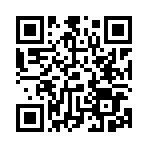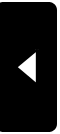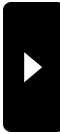2018年04月01日
3月31日(土) 当別丸山
当別丸山(482.3m)は北斗市トラピスト修道院の裏にある一等三角点の山で、山頂を北斗市と木古内町の市町境が通っている。4月1日(日)予定の北斗市自然に親しむ会主催「第18回早春トレッキング」に向けて、ルートの下見と整備を兼ねた会山行が実施された。参加は会員18名のほか、「北斗市自然に親しむ会」など3名の、計21名。
9時35分、春の軟らかな陽が射す中、修道院裏手の駐車場を20名で出発。

杉の植林地帯から階段の短縮ルートを辿って、礼拝の場である「ルルドの洞窟」に向かう。前方に白いマリア像が見えている。

階段の途中で見かけた、メタリックブルーの昆虫。後で調べたところ、「ツチハンミョウ」の仲間と判明。この昆虫は羽根が退化して飛ぶことができない。触ると死んだ振りをして脚の関節から黄色い液体を分泌するが、これには毒成分の「カンタリジン」が含まれ、弱い皮膚に付けば水膨れを生じるという。決して触らないようにしたい。

「ルルドの洞窟」があるテラスに上がった所で最初の休憩。ここまで20分。

「ルルドの洞窟」の脇に立つ白いマリア像。秋には壁を這う蔦の紅葉と、色彩の対比が美しい。

ここからの登山道は、修道院で使う薪の運び出しなど、昔の生活道路の跡でもある。木枝を片付けながら進む。

展望台への分岐付近は日当たりが良く、雪は残っていない。ナニワズが咲き始めていた。

10時20分、展望台に到着。湾越しに霞む函館山を望む。

足元には修道院の全貌が俯瞰できる。

展望台から、尾根上に付けられた道を進む。C270m付近、ブナ林の広い雪尾根は気分が良い。

C400m付近の細尾根の急登部を進む。時折、足が20~30cm埋まる。画面左の樹間越しに、函館・江差自動車道の工事現場が見える。

傾斜が緩み、右奥に頂上が見えてきた。11時20分、山頂に到着(登り1時間45分[休憩を含む])。積雪は、まだ1mほどもある。

昭和29年7月、地理調査所(現・国土地理院)によって選定された天測点。恒星などの高度角、方位角、時刻を観測し、その観測地点の地球上での位置(経度、緯度)、方位を定める天体測量に使われた。測量機器の重量に耐えられるコンクリート製の観測台座で、全国48か所(北海道8か所)に作られた一つという。当別丸山の台座には、「第七号」のプレートがはめ込まれている。

山頂で昼食を摂っていると、足の怪我の療養中だった会員のAmさんが後追いで登ってきた。皆で驚きと歓迎の拍手! 昼食を済ませ、全体写真に納まる。緑色の山頂標識は、会員だったJさん(故人)の作。11時55分、下山開始。

下山途中、尾根が細くて急になっている箇所に、翌日の安全のためロープ(50m×2本)を設置した。

上層雲が広がってきたが、まだ薄日の射す中、ゆったりとブナ林尾根を下る。

日暈が見え、その上端に上部タンジェント・アークが重なって見えた。

13時10分、駐車場に到着(下り1時間15分[ロープ設置、休憩を含む])。帰り支度を済ませ、リーダーの締めで解散した。

数分後には、修道院正面の売店でソフトクリームを買い求めるため再会。皆さん、満足して帰宅された。
9時35分、春の軟らかな陽が射す中、修道院裏手の駐車場を20名で出発。

杉の植林地帯から階段の短縮ルートを辿って、礼拝の場である「ルルドの洞窟」に向かう。前方に白いマリア像が見えている。

階段の途中で見かけた、メタリックブルーの昆虫。後で調べたところ、「ツチハンミョウ」の仲間と判明。この昆虫は羽根が退化して飛ぶことができない。触ると死んだ振りをして脚の関節から黄色い液体を分泌するが、これには毒成分の「カンタリジン」が含まれ、弱い皮膚に付けば水膨れを生じるという。決して触らないようにしたい。

「ルルドの洞窟」があるテラスに上がった所で最初の休憩。ここまで20分。

「ルルドの洞窟」の脇に立つ白いマリア像。秋には壁を這う蔦の紅葉と、色彩の対比が美しい。

ここからの登山道は、修道院で使う薪の運び出しなど、昔の生活道路の跡でもある。木枝を片付けながら進む。

展望台への分岐付近は日当たりが良く、雪は残っていない。ナニワズが咲き始めていた。

10時20分、展望台に到着。湾越しに霞む函館山を望む。

足元には修道院の全貌が俯瞰できる。

展望台から、尾根上に付けられた道を進む。C270m付近、ブナ林の広い雪尾根は気分が良い。

C400m付近の細尾根の急登部を進む。時折、足が20~30cm埋まる。画面左の樹間越しに、函館・江差自動車道の工事現場が見える。

傾斜が緩み、右奥に頂上が見えてきた。11時20分、山頂に到着(登り1時間45分[休憩を含む])。積雪は、まだ1mほどもある。

昭和29年7月、地理調査所(現・国土地理院)によって選定された天測点。恒星などの高度角、方位角、時刻を観測し、その観測地点の地球上での位置(経度、緯度)、方位を定める天体測量に使われた。測量機器の重量に耐えられるコンクリート製の観測台座で、全国48か所(北海道8か所)に作られた一つという。当別丸山の台座には、「第七号」のプレートがはめ込まれている。

山頂で昼食を摂っていると、足の怪我の療養中だった会員のAmさんが後追いで登ってきた。皆で驚きと歓迎の拍手! 昼食を済ませ、全体写真に納まる。緑色の山頂標識は、会員だったJさん(故人)の作。11時55分、下山開始。

下山途中、尾根が細くて急になっている箇所に、翌日の安全のためロープ(50m×2本)を設置した。

上層雲が広がってきたが、まだ薄日の射す中、ゆったりとブナ林尾根を下る。

日暈が見え、その上端に上部タンジェント・アークが重なって見えた。

13時10分、駐車場に到着(下り1時間15分[ロープ設置、休憩を含む])。帰り支度を済ませ、リーダーの締めで解散した。

数分後には、修道院正面の売店でソフトクリームを買い求めるため再会。皆さん、満足して帰宅された。
Posted by まるさん at 19:09│Comments(0)
│登山、山岳、山登り、アウトドア