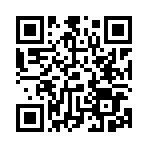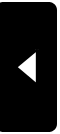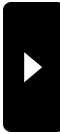2019年03月18日
3月17日(日) 熊泊山
熊泊山(くまどまりやま、817.9m)は、函館市(旧・南茅部町)と鹿部町の市町境に位置している。登りの所要時間は2時間弱と短く、780mピークまで登った後は快適な尾根歩きと素晴らしい展望が楽しめる。参加は31名。
黒羽尻川の河口付近で車7台に乗り合わせ、林道に入る。道は除雪されていたが、登るにつれて路面の積雪が深くなった。C480付近の熊泊山取り付き地点では、スコップをフル動員して駐車スペースを確保した。「除雪で疲れたから帰ろうか」の冗談も出るなか、スノーシュー・わかんを装着し、リーダーから注意事項を伝達して10時10分に出発。

780mピークから北に延びる市町境尾根(以下「北尾根」という)の末端に取り付くため、樹林帯を西に向って進む。

北尾根末端のやや急な斜面を、ジグを切って登る。ここ一週間の降雪により、新雪が20cm(上部では30cm)ほど積もっていた。

少し緩やかになったところで、樹林越しに駒ヶ岳を眺めながら一息。

北尾根上部の東側は雪庇が発達している。右手の樹林帯からあまり外れないよう、慎重にルートを見定めて登る。

北尾根の細くて急な箇所を過ぎて、間もなく780mピークに到着するところ。

780mピークで南方の展望が一気に開ける。山々を同定しながら休憩。

頂上に向かう明るい稜線を進む。心配した雪庇はあまり発達していなかったが、最近は稜線上に灌木が目立つようになり、通過に煩わしい箇所もあった。

稜線漫歩はわずか450mの距離だが、楽しいひとときである。31人も歩くと「高速道路」ができ上がる。

この頂上を初めて踏むメンバーを先頭にして、12時少し前、雪庇が張り出している頂上に到着。

頂上から横津岳方面を眺めて歓声を上げるメンバーも…。

常呂川を挟んだ東に鹿部丸山(909.2m)。最高点は、平坦に見える山頂部の右端にある。

横津岳から烏帽子岳、袴腰岳に至る横津連峰を望む。

熊泊山から烏帽子岳に繋がる、やや複雑な地形の稜線。これも、函館市(旧・南茅部町)と鹿部町の市町境を成している。
![烏帽子岳[右の雪山]に続く市町境稜線 烏帽子岳[右の雪山]に続く市町境稜線](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190317-N%E7%86%8A%E6%B3%8A%E5%B1%B1k%E7%83%8F%E5%B8%BD%E5%AD%90%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%E3%81%AE%E9%9B%AA%E5%B1%B1%5D%E3%81%AB%E7%B6%9A%E3%81%8F%E5%B8%82%E7%94%BA%E5%A2%83%E7%A8%9C%E7%B7%9Ak.jpg)
南南東には三森山(842.1m)。馴れ親しんだ三つのピークを持つ姿には見えない。

さらに、東には泣面山(834.9m)。右の黒っぽい山は803mピーク。この右奥に古部丸山が少しの間、見えていた。

横津連峰を背景にして、恒例の頂上集合写真。

西風が当たらない窪地で、ランチタイムとする。


12時35分に山頂を出発し、13時25分に下山終了。駐車場所で挨拶を済ませ、入浴は車毎として解散した。780mピークまでの登りは思わぬ深雪で、先頭グループはラッセルとルート選びに若干苦労したが、その後は快適な尾根歩きが楽しめた。まずまずの天気と展望に恵まれた一日であった。
なお、参加者が多くてリーダーの眼が届かないこともあるため、男性のOkさんとSyさんには隊列の中で前後のメンバーに目配りやサポートをしていただいた。また、女性のYhさんとMsさんには、先頭グループでラッセルをしていただいた。ありがとうございました。
黒羽尻川の河口付近で車7台に乗り合わせ、林道に入る。道は除雪されていたが、登るにつれて路面の積雪が深くなった。C480付近の熊泊山取り付き地点では、スコップをフル動員して駐車スペースを確保した。「除雪で疲れたから帰ろうか」の冗談も出るなか、スノーシュー・わかんを装着し、リーダーから注意事項を伝達して10時10分に出発。

780mピークから北に延びる市町境尾根(以下「北尾根」という)の末端に取り付くため、樹林帯を西に向って進む。

北尾根末端のやや急な斜面を、ジグを切って登る。ここ一週間の降雪により、新雪が20cm(上部では30cm)ほど積もっていた。

少し緩やかになったところで、樹林越しに駒ヶ岳を眺めながら一息。

北尾根上部の東側は雪庇が発達している。右手の樹林帯からあまり外れないよう、慎重にルートを見定めて登る。

北尾根の細くて急な箇所を過ぎて、間もなく780mピークに到着するところ。

780mピークで南方の展望が一気に開ける。山々を同定しながら休憩。

頂上に向かう明るい稜線を進む。心配した雪庇はあまり発達していなかったが、最近は稜線上に灌木が目立つようになり、通過に煩わしい箇所もあった。

稜線漫歩はわずか450mの距離だが、楽しいひとときである。31人も歩くと「高速道路」ができ上がる。

この頂上を初めて踏むメンバーを先頭にして、12時少し前、雪庇が張り出している頂上に到着。

頂上から横津岳方面を眺めて歓声を上げるメンバーも…。

常呂川を挟んだ東に鹿部丸山(909.2m)。最高点は、平坦に見える山頂部の右端にある。

横津岳から烏帽子岳、袴腰岳に至る横津連峰を望む。

熊泊山から烏帽子岳に繋がる、やや複雑な地形の稜線。これも、函館市(旧・南茅部町)と鹿部町の市町境を成している。
![烏帽子岳[右の雪山]に続く市町境稜線 烏帽子岳[右の雪山]に続く市町境稜線](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190317-N%E7%86%8A%E6%B3%8A%E5%B1%B1k%E7%83%8F%E5%B8%BD%E5%AD%90%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%E3%81%AE%E9%9B%AA%E5%B1%B1%5D%E3%81%AB%E7%B6%9A%E3%81%8F%E5%B8%82%E7%94%BA%E5%A2%83%E7%A8%9C%E7%B7%9Ak.jpg)
南南東には三森山(842.1m)。馴れ親しんだ三つのピークを持つ姿には見えない。

さらに、東には泣面山(834.9m)。右の黒っぽい山は803mピーク。この右奥に古部丸山が少しの間、見えていた。

横津連峰を背景にして、恒例の頂上集合写真。

西風が当たらない窪地で、ランチタイムとする。


12時35分に山頂を出発し、13時25分に下山終了。駐車場所で挨拶を済ませ、入浴は車毎として解散した。780mピークまでの登りは思わぬ深雪で、先頭グループはラッセルとルート選びに若干苦労したが、その後は快適な尾根歩きが楽しめた。まずまずの天気と展望に恵まれた一日であった。
なお、参加者が多くてリーダーの眼が届かないこともあるため、男性のOkさんとSyさんには隊列の中で前後のメンバーに目配りやサポートをしていただいた。また、女性のYhさんとMsさんには、先頭グループでラッセルをしていただいた。ありがとうございました。
Posted by まるさん at 23:14│Comments(0)
│登山、山岳、山登り、アウトドア