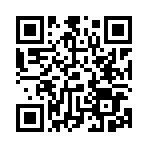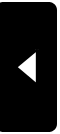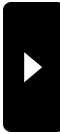2019年04月23日
4月21日(日) 太鼓山~俄虫沢
4月の自然部山行は、春到来を告げる花々が満喫できる太鼓山(171m)から俄虫沢をゆったりと辿った。参加は23名(フリー参加3名を含む)。
この時期本来の気温で、気持ち良い青空が広がる中を9時35分に出発。

先ずは地味なオクノカンスゲ(奥の寒菅)から。

キクザキイチゲ(菊咲一華)は、この時期の常連メンバー。花の咲き始めは、少し色の付いた個体も…。


これも常連のカタクリ(片栗)は、場所によって一面の群落を形成している。

他のスミレに比べて距(花の萼や花冠の基部近くから突出した部分)が長いことから、ナガハシスミレ(長嘴菫)と名付けられた。別名のテングスミレ(天狗菫)も同じような意味で、長い距を天狗の鼻に見立てたもの。

エゾエンゴサク(蝦夷延胡索)は淡い青色の可憐な花が特徴だが、色は個体によって少しずつ異なる。空色、少し濃い青色、二色混合…。右下は、葉が細いホソバエゾエンゴサク。

エンレイソウ(延齢草)も主役。この辺りには「黒実」が多いようだが、たまに「白実」も…。


途中で立ち止まりながら、山野草や樹木、岩石の実物を前にして、詳しいメンバーから解説を聞く「自然部」山行のひとこま。

ヒトリシズカ(一人静)。別の場所では、これが何十人も…。

フキ(蕗、苳など)は雄株と雌株を分けることで、自家受粉を巧みに避けている。雄株(右)の花は花粉のためか黄色っぽく見えるのに対し、雌株(左)の花は白く見える。
![フキの雌株[左]と雄株[右] フキの雌株[左]と雄株[右]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190421-L%E5%A4%AA%E9%BC%93%E5%B1%B1k%E4%BF%84%E8%99%AB%E6%B2%A2k%E3%83%95%E3%82%AD%E3%81%AE%E9%9B%8C%E6%A0%AA%5B%E5%B7%A6%5D%E3%81%A8%E9%9B%84%E6%A0%AAk.jpg)
キブシ(木五倍子)は、北海道西南部から南の地方に分布する。名前は、実が染料に使われるヌルデの五倍子(ブシ)の代用になったことによる。

センボンヤリ(千本槍)の花を見かけた。春と秋に2回花を付けるが、秋の花は蕾のまま開かずに茶色い穂先になり、これが大名行列の毛槍に似ることが名前の由来。

可憐なフデリンドウ(筆竜胆)も…。

太鼓山の頂上で、最初の全体写真を撮る。前列向かって左から二人目のAtさんが持つ岩石のうち、左手のチャートは、堆積岩の一種。主成分は二酸化ケイ素(石英)で、石英質の骨格を持った海生浮遊性原生動物の一種である放散虫の化石が海底に堆積・密集してできた。断面をルーペで見ると、放散虫の殻が点状に見えるものもある。右手の珪岩(けいがん)は、チャートや珪質砂岩が地中深くで熱による変成を受けた変成岩。いずれも太鼓山を形成する代表的な岩石である(Ttさんの解説による)。

俄虫沢に向かう途中で見かけたスミレサイシン(菫細辛)は、北海道西部~山口県までの日本海側のあまり高くない山地が主体で、半日陰の落葉樹林下などを好む多年草。葉はハート形で先が尖る。ふつう、花期には写真下のように縮れていることが多い。

登山道から少し離れた樹木の幹に開けられたクマゲラの食痕。幹の中に巣くう蟻を食餌とするために掘ったもので、縦に長い矩形をしているのが特徴。

俄虫沢に降り立つと、これまでに見られた花のほか、キバナノアマナ(黄花の甘菜)やフクジュソウ(福寿草)の黄色も目についた。


沢の斜面は、まさに百花繚乱…。

そして、俄虫沢の主役であるエゾノリュウキンカ(蝦夷立金花)の群落が広がる。北海道ではヤチブキ(谷地蕗)とも呼ぶ。満開は、あと数日先のようだ。

流れの畔にミズバショウ(水芭蕉)。

俄虫沢のエゾノリュウキンカ群落を背景に、二度目の全体写真を撮る。

沢出口にある溜池堰堤の下でゆったりと昼食を摂り、駐車場に戻る。キタコブシ(北辛夷)の花は、ようやく開き始めた段階だった。

残雪をまとった乙部岳(1016.9m)。

いつもの畦道を通って、13時ちょうど駐車場にゴール。

太鼓山から俄虫沢を辿って3時間25分(昼食35分を含む)、いつにも増してゆったりと自然に親しむことができた。駐車場で全体の挨拶を済ませ、車毎に解散した。なお、車2台のメンバーは近くの「土橋自然観察教育林・レクの森」で、Ttさんによる追加の植物学習・鑑賞会となった。
この時期本来の気温で、気持ち良い青空が広がる中を9時35分に出発。

先ずは地味なオクノカンスゲ(奥の寒菅)から。

キクザキイチゲ(菊咲一華)は、この時期の常連メンバー。花の咲き始めは、少し色の付いた個体も…。


これも常連のカタクリ(片栗)は、場所によって一面の群落を形成している。

他のスミレに比べて距(花の萼や花冠の基部近くから突出した部分)が長いことから、ナガハシスミレ(長嘴菫)と名付けられた。別名のテングスミレ(天狗菫)も同じような意味で、長い距を天狗の鼻に見立てたもの。

エゾエンゴサク(蝦夷延胡索)は淡い青色の可憐な花が特徴だが、色は個体によって少しずつ異なる。空色、少し濃い青色、二色混合…。右下は、葉が細いホソバエゾエンゴサク。

エンレイソウ(延齢草)も主役。この辺りには「黒実」が多いようだが、たまに「白実」も…。


途中で立ち止まりながら、山野草や樹木、岩石の実物を前にして、詳しいメンバーから解説を聞く「自然部」山行のひとこま。

ヒトリシズカ(一人静)。別の場所では、これが何十人も…。

フキ(蕗、苳など)は雄株と雌株を分けることで、自家受粉を巧みに避けている。雄株(右)の花は花粉のためか黄色っぽく見えるのに対し、雌株(左)の花は白く見える。
![フキの雌株[左]と雄株[右] フキの雌株[左]と雄株[右]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190421-L%E5%A4%AA%E9%BC%93%E5%B1%B1k%E4%BF%84%E8%99%AB%E6%B2%A2k%E3%83%95%E3%82%AD%E3%81%AE%E9%9B%8C%E6%A0%AA%5B%E5%B7%A6%5D%E3%81%A8%E9%9B%84%E6%A0%AAk.jpg)
キブシ(木五倍子)は、北海道西南部から南の地方に分布する。名前は、実が染料に使われるヌルデの五倍子(ブシ)の代用になったことによる。

センボンヤリ(千本槍)の花を見かけた。春と秋に2回花を付けるが、秋の花は蕾のまま開かずに茶色い穂先になり、これが大名行列の毛槍に似ることが名前の由来。

可憐なフデリンドウ(筆竜胆)も…。

太鼓山の頂上で、最初の全体写真を撮る。前列向かって左から二人目のAtさんが持つ岩石のうち、左手のチャートは、堆積岩の一種。主成分は二酸化ケイ素(石英)で、石英質の骨格を持った海生浮遊性原生動物の一種である放散虫の化石が海底に堆積・密集してできた。断面をルーペで見ると、放散虫の殻が点状に見えるものもある。右手の珪岩(けいがん)は、チャートや珪質砂岩が地中深くで熱による変成を受けた変成岩。いずれも太鼓山を形成する代表的な岩石である(Ttさんの解説による)。

俄虫沢に向かう途中で見かけたスミレサイシン(菫細辛)は、北海道西部~山口県までの日本海側のあまり高くない山地が主体で、半日陰の落葉樹林下などを好む多年草。葉はハート形で先が尖る。ふつう、花期には写真下のように縮れていることが多い。

登山道から少し離れた樹木の幹に開けられたクマゲラの食痕。幹の中に巣くう蟻を食餌とするために掘ったもので、縦に長い矩形をしているのが特徴。

俄虫沢に降り立つと、これまでに見られた花のほか、キバナノアマナ(黄花の甘菜)やフクジュソウ(福寿草)の黄色も目についた。


沢の斜面は、まさに百花繚乱…。

そして、俄虫沢の主役であるエゾノリュウキンカ(蝦夷立金花)の群落が広がる。北海道ではヤチブキ(谷地蕗)とも呼ぶ。満開は、あと数日先のようだ。

流れの畔にミズバショウ(水芭蕉)。

俄虫沢のエゾノリュウキンカ群落を背景に、二度目の全体写真を撮る。

沢出口にある溜池堰堤の下でゆったりと昼食を摂り、駐車場に戻る。キタコブシ(北辛夷)の花は、ようやく開き始めた段階だった。

残雪をまとった乙部岳(1016.9m)。

いつもの畦道を通って、13時ちょうど駐車場にゴール。

太鼓山から俄虫沢を辿って3時間25分(昼食35分を含む)、いつにも増してゆったりと自然に親しむことができた。駐車場で全体の挨拶を済ませ、車毎に解散した。なお、車2台のメンバーは近くの「土橋自然観察教育林・レクの森」で、Ttさんによる追加の植物学習・鑑賞会となった。
Posted by まるさん at 22:28│Comments(0)
│登山、山岳、山登り、アウトドア