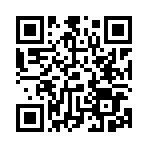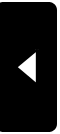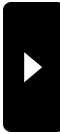2019年06月11日
6月9日(日) 昆布岳
豊浦町とニセコ町の境に聳える昆布岳(1,044.9m)を訪れた。山名はアイヌ語の「コンポ・ヌプリ」(小さなコブ山)から転化したそうで、なだらかな裾野と尖った山頂部が目立つ。一等三角点が設置された頂上からは、羊蹄山やニセコ連峰、洞爺湖などの眺望が良い。参加は17名。
豊浦町・道道914号線「上泉」地区の登山用駐車場は、登山や山菜採りの車で満杯であった。ここを8時5分に出発し、広い尾根道を緩やかに登っていく。写真は二合目付近。

登山道脇で、春から初夏の花々が迎えてくれる。ツクバネソウ[衝羽根草](左上)、オオアマドコロ[大甘野老](右上)、ツボスミレ[坪菫]・別名ニョイスミレ[如意菫](左下)、タチツボスミレ[立坪菫](右下)。

C550の古い林道との交差点(三・五合目)で、休憩を兼ねて読図の学習を実施。五合目近くになっても登山道の周りの植生に大きな変化がないが、樹木は樺が目立ってきた。

五合目付近で見かけたノウゴウイチゴ[能郷苺]は、鋸歯状の葉先ごとに丸い水滴を付けていた。S先生によると、葉先にある「水孔」から余分な水分が押し出されているとのことで、気温が下がる(湿度が高い)朝に良くみられるようだ。フキの葉先でも、同じ現象が見られた。
![ノウゴウイチゴ[能郷苺] ノウゴウイチゴ[能郷苺]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190609-D%E6%98%86%E5%B8%83%E5%B2%B3k%E3%83%8E%E3%82%A6%E3%82%B4%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%B4%5B%E8%83%BD%E9%83%B7%E8%8B%BA%5Dk.jpg)
五合目を過ぎ、「メガネ岩」に到着。昆布岳火山体の古い溶岩によるもので、岩質は「白濁した斜長石の目立つガラス質輝石安山岩」(ネット検索)とのこと。三々五々、岩のアーチを探訪する。

かなり細かい柱状節理が発達している。その「メガネ」部分を額縁にして、一枚パチリ。

岩肌に水平に付いた溝に、多くのミヤマオダマキ[深山苧環]が今を盛りと咲き誇っていた。岩壁の下部と上部に見られた株の姿をどうぞ。


九合目に達すると、ようやく周りの視界が開けてくる。本峰の東尾根と911m峰(右)を望む。
![九合目から本峰東尾根[右は911m峰] 九合目から本峰東尾根[右は911m峰]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190609-I%E6%98%86%E5%B8%83%E5%B2%B3k%E4%B9%9D%E5%90%88%E7%9B%AE%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9C%AC%E5%B3%B0%E6%9D%B1%E5%B0%BE%E6%A0%B9%5B%E5%8F%B3%E3%81%AF911m%E5%B3%B0%5Dk.jpg)
ここから最後の急登が始まる。

雪が消えたばかりの登山道脇には、春の花が見られた。エンレイソウ[延齢草]の実(左上、これは五合目付近で)、エゾイチゲ[蝦夷一華](右上)、サンカヨウ[山荷葉](左下)、シラネアオイ[白根葵](右下)。

そして、ハクサンチドリ[白山千鳥](左上)、ヤマタネツケバナ[山種漬花](右上)、ツバメオモト[燕万年青](左下)、ウコンウツギ[鬱金空木](右下、これは頂上で)。

頂上直下の露岩帯から、南西の944m峰を望む。

11時20分、頂上に到着。新しくなった「昆布」形の標識が出迎えてくれた。初めて頂上に立った会員のみの限定写真2枚。


頂上からの展望は低い雲のため今ひとつだったが、時折り雲が切れると、真北にニセコ連峰が望めた。

北東の後方羊蹄山(1,898m)は、山頂が雲の中。

恒例の全体写真を撮って11時55分、頂上を後にする。

下山中に見られた花は、クロツリバナ[黒吊花](左上)、ガマズミ[莢蒾](右上)、ホオノキ[朴の木](左下)、ベニバナイチヤクソウ[紅花一薬草](右下)。Tさんによると、クロツリバナは、本州中部以北の亜高山帯(道南ではダケカンバ帯に相当)に生育するとのこと。

14時20分、登山口駐車場に到着して下山終了。挨拶の後に現地で解散し、車ごとに入浴して帰宅した。頂上からの眺めは今ひとつだったが、写しきれないほど多くの花と出会うことができた良い山行だった。
豊浦町・道道914号線「上泉」地区の登山用駐車場は、登山や山菜採りの車で満杯であった。ここを8時5分に出発し、広い尾根道を緩やかに登っていく。写真は二合目付近。

登山道脇で、春から初夏の花々が迎えてくれる。ツクバネソウ[衝羽根草](左上)、オオアマドコロ[大甘野老](右上)、ツボスミレ[坪菫]・別名ニョイスミレ[如意菫](左下)、タチツボスミレ[立坪菫](右下)。

C550の古い林道との交差点(三・五合目)で、休憩を兼ねて読図の学習を実施。五合目近くになっても登山道の周りの植生に大きな変化がないが、樹木は樺が目立ってきた。

五合目付近で見かけたノウゴウイチゴ[能郷苺]は、鋸歯状の葉先ごとに丸い水滴を付けていた。S先生によると、葉先にある「水孔」から余分な水分が押し出されているとのことで、気温が下がる(湿度が高い)朝に良くみられるようだ。フキの葉先でも、同じ現象が見られた。
![ノウゴウイチゴ[能郷苺] ノウゴウイチゴ[能郷苺]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190609-D%E6%98%86%E5%B8%83%E5%B2%B3k%E3%83%8E%E3%82%A6%E3%82%B4%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%B4%5B%E8%83%BD%E9%83%B7%E8%8B%BA%5Dk.jpg)
五合目を過ぎ、「メガネ岩」に到着。昆布岳火山体の古い溶岩によるもので、岩質は「白濁した斜長石の目立つガラス質輝石安山岩」(ネット検索)とのこと。三々五々、岩のアーチを探訪する。

かなり細かい柱状節理が発達している。その「メガネ」部分を額縁にして、一枚パチリ。

岩肌に水平に付いた溝に、多くのミヤマオダマキ[深山苧環]が今を盛りと咲き誇っていた。岩壁の下部と上部に見られた株の姿をどうぞ。


九合目に達すると、ようやく周りの視界が開けてくる。本峰の東尾根と911m峰(右)を望む。
![九合目から本峰東尾根[右は911m峰] 九合目から本峰東尾根[右は911m峰]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190609-I%E6%98%86%E5%B8%83%E5%B2%B3k%E4%B9%9D%E5%90%88%E7%9B%AE%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9C%AC%E5%B3%B0%E6%9D%B1%E5%B0%BE%E6%A0%B9%5B%E5%8F%B3%E3%81%AF911m%E5%B3%B0%5Dk.jpg)
ここから最後の急登が始まる。

雪が消えたばかりの登山道脇には、春の花が見られた。エンレイソウ[延齢草]の実(左上、これは五合目付近で)、エゾイチゲ[蝦夷一華](右上)、サンカヨウ[山荷葉](左下)、シラネアオイ[白根葵](右下)。

そして、ハクサンチドリ[白山千鳥](左上)、ヤマタネツケバナ[山種漬花](右上)、ツバメオモト[燕万年青](左下)、ウコンウツギ[鬱金空木](右下、これは頂上で)。

頂上直下の露岩帯から、南西の944m峰を望む。

11時20分、頂上に到着。新しくなった「昆布」形の標識が出迎えてくれた。初めて頂上に立った会員のみの限定写真2枚。


頂上からの展望は低い雲のため今ひとつだったが、時折り雲が切れると、真北にニセコ連峰が望めた。

北東の後方羊蹄山(1,898m)は、山頂が雲の中。

恒例の全体写真を撮って11時55分、頂上を後にする。

下山中に見られた花は、クロツリバナ[黒吊花](左上)、ガマズミ[莢蒾](右上)、ホオノキ[朴の木](左下)、ベニバナイチヤクソウ[紅花一薬草](右下)。Tさんによると、クロツリバナは、本州中部以北の亜高山帯(道南ではダケカンバ帯に相当)に生育するとのこと。

14時20分、登山口駐車場に到着して下山終了。挨拶の後に現地で解散し、車ごとに入浴して帰宅した。頂上からの眺めは今ひとつだったが、写しきれないほど多くの花と出会うことができた良い山行だった。
Posted by まるさん at 16:53│Comments(0)
│登山、山岳、山登り、アウトドア