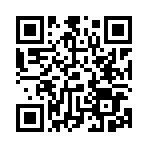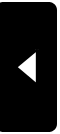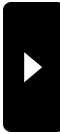2019年06月06日
6月6日(水) 6月例会
道内の最高気温を更新し、異例の猛暑となった5月が終わり、爽やかな?6月の始まり。今回も、暑かったが青空に恵まれ沢山のお花に会えた山行だった。
5月の行事報告
5月5日(日)小幌
トンネル脇から沢を下り秘境駅へ、ちょうど列車の通過に遭遇。その後、円空の仏像(レプリカ)のある岩屋海岸へ、ちょうど干潮で岩棚の上を歩くことができた。帰りは来た時とは別の、両側ニリンソウロードの中を登り出発地点まで戻った。
5月12日(日)ヤンカ山
今回は4年前の秋に行ったルートと反対の反時計回り。東尾根の西側の斜面にオオサクラソウの群落があった。細尾根は慎重に通過。下りの川に降りる所の急所にはロープが張られていた。花の時期もコースもほぼ正解であった。
5月16日(木)毛無山整備登山
急登に設置されていた、20年近く経っていると思われる古いロープを取り換え、桧沢の滝までの橋(7カ所)を補修。立派な登山道が出来上がった。
5月19日(日)伊達紋別岳
天気に恵まれ、登山開始からすでに暑かった。途中多くの花が見られ、稜線に出るとブーケのようなシラネアオイ群落(白バナシラネアオイも。)が見られた。眺望も良くすぐそこに稀府岳、雪をかぶった羊蹄山、ニセコ連峰、徳舜瞥・ホロホロとぐるりと見渡せた。
5月27日(月)烏帽子岳 笹狩り
昨年度、刈残した烏帽子岳周辺の笹狩りを渡島総合振興局東部森林室の職員2名と実施。今年の秋も整備の予定。
6月2日(日)汐首岬
ゲートからアンテナ群、その後通称203高地へ沢山の花を観察しながらのハイキング。海岸線の美しさを見ながら、森林地帯を歩くのとはまた違った趣のある道だった。そして、斜面に色の濃いエゾヤマツツジが見事に咲いていた。
6月の行事予定
昆布岳 長万部岳 大千軒岳(知内コース)
学習会 『屋外で雷を避けるために』
高い木の下などには行かない。ザックなど自分の頭より高いものは地面におろす。小屋に避難した場合は壁に雷が走ることがあるので、壁の方には近づかないで真ん中にいたほうが良い。
雷を避ける体勢をみんなでやってみました!両足の間隔を狭くして、膝を抱えてしゃがむ。お尻を地面に付けて座らない(落雷があったとき地面を電流が流れることがある。ザックの上に座るのもダメ。)。両耳を塞ぐ。そのまま雷が収まるまで30~45分くらい待つ。・・・・続きは次回の学習会で・・・・・
5月の行事報告
5月5日(日)小幌
トンネル脇から沢を下り秘境駅へ、ちょうど列車の通過に遭遇。その後、円空の仏像(レプリカ)のある岩屋海岸へ、ちょうど干潮で岩棚の上を歩くことができた。帰りは来た時とは別の、両側ニリンソウロードの中を登り出発地点まで戻った。
5月12日(日)ヤンカ山
今回は4年前の秋に行ったルートと反対の反時計回り。東尾根の西側の斜面にオオサクラソウの群落があった。細尾根は慎重に通過。下りの川に降りる所の急所にはロープが張られていた。花の時期もコースもほぼ正解であった。
5月16日(木)毛無山整備登山
急登に設置されていた、20年近く経っていると思われる古いロープを取り換え、桧沢の滝までの橋(7カ所)を補修。立派な登山道が出来上がった。
5月19日(日)伊達紋別岳
天気に恵まれ、登山開始からすでに暑かった。途中多くの花が見られ、稜線に出るとブーケのようなシラネアオイ群落(白バナシラネアオイも。)が見られた。眺望も良くすぐそこに稀府岳、雪をかぶった羊蹄山、ニセコ連峰、徳舜瞥・ホロホロとぐるりと見渡せた。
5月27日(月)烏帽子岳 笹狩り
昨年度、刈残した烏帽子岳周辺の笹狩りを渡島総合振興局東部森林室の職員2名と実施。今年の秋も整備の予定。
6月2日(日)汐首岬
ゲートからアンテナ群、その後通称203高地へ沢山の花を観察しながらのハイキング。海岸線の美しさを見ながら、森林地帯を歩くのとはまた違った趣のある道だった。そして、斜面に色の濃いエゾヤマツツジが見事に咲いていた。
6月の行事予定
昆布岳 長万部岳 大千軒岳(知内コース)
学習会 『屋外で雷を避けるために』
高い木の下などには行かない。ザックなど自分の頭より高いものは地面におろす。小屋に避難した場合は壁に雷が走ることがあるので、壁の方には近づかないで真ん中にいたほうが良い。
雷を避ける体勢をみんなでやってみました!両足の間隔を狭くして、膝を抱えてしゃがむ。お尻を地面に付けて座らない(落雷があったとき地面を電流が流れることがある。ザックの上に座るのもダメ。)。両耳を塞ぐ。そのまま雷が収まるまで30~45分くらい待つ。・・・・続きは次回の学習会で・・・・・

2019年06月04日
6月2日 汐首岬
6月の自然部山行は汐首岬。昨年は6月中旬でエゾヤマツツジはもう終わっていた(昨年の模様はこちらをご覧ください)。それで今年は半月早く行ってみることにした。爽やかな風の吹く,快晴の天気の下,26名で出発。
準備を済ませて9時50分ゲートを出発。

最初に見られた花はタニウツギ(左上)・ミツバウツギ(右上)・カマツカ(左下)・カンボク(右下)。

キンギンボク(ヒョウタンボク)はなぜ一つの木に白と黄色の花があるのかという疑問にTさんが説明を加えてくれた。当日は黄色が先で受粉後白くなるということでしたが,後日以下のように訂正されました。花の咲き始めは白色で次第に黄色になるとのこと。色の変化に受粉が関係しているかどうかは今のところよくわからない。ただ虫の眼には白色の方が目立つとのことでした。受粉のために目立つ必要がなくなると黄色からさらに褐色へと変色するようです。


また少し先のナラの若木に実のようなものがくっついていた。虫こぶ(虫嬰)というものだそうで,ナラメリンゴフシかも知れないとのこと。

C200のあたりで視界が開け,函館山がすっきり見えた。その奥には桂岳,左に当別丸山。

次の花はオヤマボクチ(左上)・エゾカンゾウ(右上)・エゾヤマツツジ(左下)・アキグミ(右下)。

C210あたりから下海岸を俯瞰する。霞む函館市街へと海岸線が伸びている。

C250付近の林道を行く。

この辺りで見かけたヒメイズイを太陽とともにパチリ。

しばらく津軽海峡や津軽半島を遠くに見ながら歩く。右には知内方面も見える。

歩いていると飛行機が真上を通って行った。函館空港への着陸態勢に入っている。真上と後ろからのツーショット。

アンテナ群まで来るといつものように馬がいた。こちらは道産子ではない。仔馬も見られた。

12時近くになったので昼食とする。恵山も褐色と白い山肌を見せていた。

昼食を済ませ,通称203高地(285ポコ)へ向かう。途中見られた花はハイキンポウゲ(左上)・ミミナグサ属(右上)・フランスギク(左下)・チシマフウロ(右下)。

280ポコを林道沿いに迂回せず,真っ直ぐ登ったメンバーが下りてくるところを撮った。

203高地へ向かう日本軍? 往きは林道,帰りは高地を真っ直ぐ下りる。

林道を歩いて203高地の裏側へ回り,戻るようにして203高地へ登る。

13時過ぎに頂上着。馬が一頭(こちらは道産子)こちらを窺っている。一頭だけかと思ったら,近くの林の中に群れていた。どうやら見張り役らしい。じっとわれわれの動向を窺っている。驚かせないように行き過ぎる。285ポコの端に来て全体写真。左奥にその見張り役の馬の姿も入れておいた。

203高地を下る。今度はロシア軍気取りで一列に。

C200辺りの分岐まで来て,登って来た舗装路を帰る組と別ルートを下りる組とに分かれた。最後に見られた花は分岐にあったネバリノギラン(左上)と別ルートのエゾカンゾウ(右上)・オオアマドコロ(左下)・フタリシズカ(右下)。

13時50分に下山終了。最後にTさんが目当てにしていた紫色のヒロハテンナンショウも見つけられ,また来年の楽しみにしようということで挨拶を済ませ,車毎に解散した。
準備を済ませて9時50分ゲートを出発。

最初に見られた花はタニウツギ(左上)・ミツバウツギ(右上)・カマツカ(左下)・カンボク(右下)。

キンギンボク(ヒョウタンボク)はなぜ一つの木に白と黄色の花があるのかという疑問にTさんが説明を加えてくれた。当日は黄色が先で受粉後白くなるということでしたが,後日以下のように訂正されました。花の咲き始めは白色で次第に黄色になるとのこと。色の変化に受粉が関係しているかどうかは今のところよくわからない。ただ虫の眼には白色の方が目立つとのことでした。受粉のために目立つ必要がなくなると黄色からさらに褐色へと変色するようです。


また少し先のナラの若木に実のようなものがくっついていた。虫こぶ(虫嬰)というものだそうで,ナラメリンゴフシかも知れないとのこと。

C200のあたりで視界が開け,函館山がすっきり見えた。その奥には桂岳,左に当別丸山。

次の花はオヤマボクチ(左上)・エゾカンゾウ(右上)・エゾヤマツツジ(左下)・アキグミ(右下)。

C210あたりから下海岸を俯瞰する。霞む函館市街へと海岸線が伸びている。

C250付近の林道を行く。

この辺りで見かけたヒメイズイを太陽とともにパチリ。

しばらく津軽海峡や津軽半島を遠くに見ながら歩く。右には知内方面も見える。

歩いていると飛行機が真上を通って行った。函館空港への着陸態勢に入っている。真上と後ろからのツーショット。

アンテナ群まで来るといつものように馬がいた。こちらは道産子ではない。仔馬も見られた。

12時近くになったので昼食とする。恵山も褐色と白い山肌を見せていた。

昼食を済ませ,通称203高地(285ポコ)へ向かう。途中見られた花はハイキンポウゲ(左上)・ミミナグサ属(右上)・フランスギク(左下)・チシマフウロ(右下)。

280ポコを林道沿いに迂回せず,真っ直ぐ登ったメンバーが下りてくるところを撮った。

203高地へ向かう日本軍? 往きは林道,帰りは高地を真っ直ぐ下りる。

林道を歩いて203高地の裏側へ回り,戻るようにして203高地へ登る。

13時過ぎに頂上着。馬が一頭(こちらは道産子)こちらを窺っている。一頭だけかと思ったら,近くの林の中に群れていた。どうやら見張り役らしい。じっとわれわれの動向を窺っている。驚かせないように行き過ぎる。285ポコの端に来て全体写真。左奥にその見張り役の馬の姿も入れておいた。
203高地を下る。今度はロシア軍気取りで一列に。

C200辺りの分岐まで来て,登って来た舗装路を帰る組と別ルートを下りる組とに分かれた。最後に見られた花は分岐にあったネバリノギラン(左上)と別ルートのエゾカンゾウ(右上)・オオアマドコロ(左下)・フタリシズカ(右下)。

13時50分に下山終了。最後にTさんが目当てにしていた紫色のヒロハテンナンショウも見つけられ,また来年の楽しみにしようということで挨拶を済ませ,車毎に解散した。
2019年05月28日
5月27日(月) 烏帽子岳周辺の笹刈り(登山道整備)
昨年10月、渡島総合振興局東部森林室による横津岳~烏帽子岳縦走路の整備(笹刈り)に、当クラブも手伝いをした(こちら)。今回は、この時の残り部分を整備するため、同森林室と共同で作業に当たった。参加は会員11人と「函館マウンテンクラブ」のNさん、同森林室の職員さん2人。
先ず、烏帽子岳(1,078m)頂上に集合。ここで三チーム(それぞれに刈り払い機を操作する人、笹の片づけ・刈りこぼした笹の切り取り・邪魔な枝の処理・燃料や器械操作担当者ザックの運搬をする人)に分かれて、作業を始めた。

烏帽子岳頂上から袴腰岳に向かう際に利用する東側連絡路の笹刈りを開始。笹が1mほどの高さに延びて登山道を覆い、廃道状態になっていた。

器械が刈りこぼした笹を手鋏で切り取る。

立派な登山道が復活。

脇の「きわ剃り」整形で、より豪華に…。

二つのチームの作業によって、烏帽子岳頂上部の三角形登山道が開通した。

もう一つのチームは烏帽子岳から第二湿原近くまでの区間を担当し、これも笹刈りが開通。


第二湿原は乾燥化が進んでいる。湿原の脇は桜が真っ盛りだった。チシマザクラかミネザクラか…。

気象レーダーまで、延びてきた笹を刈り払いながら帰路につく。縦走路の脇にも、桜が咲いていた。
![桜[種類は不明] 桜[種類は不明]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190527-J%E6%A8%AA%E6%B4%A5%E5%B2%B3%E7%AC%B9%E5%88%88%E3%82%8Ak%E6%A1%9C%5B%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%AF%E4%B8%8D%E6%98%8E%5Dk.jpg)
ピンクっぽく見えるのは桜、さくら、サクラ…。桜が沢山自生していることに驚いた。

昨秋からの3回の作業により、沢山の方に利用していただける登山道が立派に復活した。今年の秋にも、登山道整備の手伝いを予定しています。
先ず、烏帽子岳(1,078m)頂上に集合。ここで三チーム(それぞれに刈り払い機を操作する人、笹の片づけ・刈りこぼした笹の切り取り・邪魔な枝の処理・燃料や器械操作担当者ザックの運搬をする人)に分かれて、作業を始めた。

烏帽子岳頂上から袴腰岳に向かう際に利用する東側連絡路の笹刈りを開始。笹が1mほどの高さに延びて登山道を覆い、廃道状態になっていた。

器械が刈りこぼした笹を手鋏で切り取る。

立派な登山道が復活。

脇の「きわ剃り」整形で、より豪華に…。

二つのチームの作業によって、烏帽子岳頂上部の三角形登山道が開通した。

もう一つのチームは烏帽子岳から第二湿原近くまでの区間を担当し、これも笹刈りが開通。


第二湿原は乾燥化が進んでいる。湿原の脇は桜が真っ盛りだった。チシマザクラかミネザクラか…。

気象レーダーまで、延びてきた笹を刈り払いながら帰路につく。縦走路の脇にも、桜が咲いていた。
![桜[種類は不明] 桜[種類は不明]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190527-J%E6%A8%AA%E6%B4%A5%E5%B2%B3%E7%AC%B9%E5%88%88%E3%82%8Ak%E6%A1%9C%5B%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%AF%E4%B8%8D%E6%98%8E%5Dk.jpg)
ピンクっぽく見えるのは桜、さくら、サクラ…。桜が沢山自生していることに驚いた。

昨秋からの3回の作業により、沢山の方に利用していただける登山道が立派に復活した。今年の秋にも、登山道整備の手伝いを予定しています。
2019年05月28日
5/26(日) 「毛無山(750m)」登山会
今年で16年目となる登山会(「北斗市自然に親しむ会」主催)は参加者71名。真夏並みの暑さの予報により出発前に注意喚起、水筒ペットボトルの用意が足りない参加者には追加でペットボトルを渡し熱中症に備えた。
国道から登山口へ。

暖冬だったせいで路肩の藪の成長が早い。

初春の花「ニリンソウ」。食用にもなるが猛毒のトリカブトと間違えやすく花が咲いてから摘み取るのが安全と言われている。

ミドリニリンソウはニリンソウの白い花弁が緑色に変わった変異体。珍しくはないが目立たないので見逃しやすい。

最初の休憩場所は「桧沢の滝」。今年は上流にあるはずの残雪も消え、滝の水量が少なく迫力不足だが「白糸」のように流れ落ちるのも良い感じだった。

休憩を終え出発準備。コース中の一番の急登が滝横の階段だ。

この山を代表する花は「サンカヨウ」。道南でも屈指の群落をつくる。

気温が高いせいか「エゾハルゼミ」の蝉しぐれが響き、春の終わりを感じる。

「ユキザサ」というより別名の「アズキナ」の方がわかりやすい。おひたしにするとほんのり甘く美味しい。

チゴユリの花言葉は「私の小さな手をいつもにぎって」や「恥ずかしがり屋さん」。

花の閉じた状態が筆の穂先に似ているので「フデリンドウ」。

オランダガラシ(クレソン)は繁殖力が強く実は要注意外来生物。

何故か村下孝蔵さんを思い出す「オドリコソウ」。

オオバミゾホオズキはあちこちで見られた。

ズダヤクシュの「ずだ」とは長野県地方の方言で「喘息」のこと。喘息の咳止薬として用いられてきた。

ノビネチドリ。チドリと名につくランは他にもたくさんある。いくつ言えますか?

ホウチャクソウかアマドコロ(知識不足で不明)。

標高620あたりのトラバースを列を作って歩いている様子。例年だと雪が残る緊張トラバースだが今年は心配なし。一部、エゾエンゴサクの群落が見られた。

国道から登山口へ。

暖冬だったせいで路肩の藪の成長が早い。

初春の花「ニリンソウ」。食用にもなるが猛毒のトリカブトと間違えやすく花が咲いてから摘み取るのが安全と言われている。

ミドリニリンソウはニリンソウの白い花弁が緑色に変わった変異体。珍しくはないが目立たないので見逃しやすい。

最初の休憩場所は「桧沢の滝」。今年は上流にあるはずの残雪も消え、滝の水量が少なく迫力不足だが「白糸」のように流れ落ちるのも良い感じだった。

休憩を終え出発準備。コース中の一番の急登が滝横の階段だ。

この山を代表する花は「サンカヨウ」。道南でも屈指の群落をつくる。

気温が高いせいか「エゾハルゼミ」の蝉しぐれが響き、春の終わりを感じる。

「ユキザサ」というより別名の「アズキナ」の方がわかりやすい。おひたしにするとほんのり甘く美味しい。

チゴユリの花言葉は「私の小さな手をいつもにぎって」や「恥ずかしがり屋さん」。

花の閉じた状態が筆の穂先に似ているので「フデリンドウ」。

オランダガラシ(クレソン)は繁殖力が強く実は要注意外来生物。

何故か村下孝蔵さんを思い出す「オドリコソウ」。

オオバミゾホオズキはあちこちで見られた。

ズダヤクシュの「ずだ」とは長野県地方の方言で「喘息」のこと。喘息の咳止薬として用いられてきた。

ノビネチドリ。チドリと名につくランは他にもたくさんある。いくつ言えますか?

ホウチャクソウかアマドコロ(知識不足で不明)。

標高620あたりのトラバースを列を作って歩いている様子。例年だと雪が残る緊張トラバースだが今年は心配なし。一部、エゾエンゴサクの群落が見られた。

2019年05月23日
5月19日 伊達紋別岳
シラネアオイの良い時期を狙って、久しぶりに伊達紋別(715m)登山。天候にも恵まれ思った通り沢山の登山者でにぎわっていた。中には私たち23名の上をいく32名の団体さんも・・・・人気のお山ですね。
10:10 登山口で出発挨拶。ここから10分くらいの所にやっと登山BOX。急登ですでに暑い!

尾根道を進む

スズラン・フデリンドウ・ミヤマエンレイソウ・ヒメイチゲ

ピンクがかったミヤマエンレイソウ

10:45 一望台(3合目)あたりの羊蹄山

そして有珠山

6合目の少し上の「ガンバレ岩」を過ぎる。帰りは反対側に「マタキテネ」

11:35 7合目「いっぷく広場」に到着

「いっぷく広場」から南東隣りの稀府岳

これから向かう前紋別岳方向

チシマフウロ・キジムシロ・ノウゴウイチゴ・ミヤマアズマギク

前紋別岳に向かう

エゾコザクラ

ミヤマオダマキ・ナツトウダイ・エゾアオイスミレ?・ハクサンチドリ

前紋別岳への最後の登り

12:15 前紋別岳から羊蹄山

紋別岳本峰を望む

シラネアオイの群落

白花のシラネアオイ

本峰への最後の登り

12:45 頂上から昆布岳と遠く目国内岳

左遠くに徳舜瞥山とホロホロ山

頂上 全体集合

頂上 全体集合 その2

昼食後 13:15下山開始 15:15登山口到着 暑さにバテましたが、沢山の花と眺望に恵まれた1日でした。
10:10 登山口で出発挨拶。ここから10分くらいの所にやっと登山BOX。急登ですでに暑い!

尾根道を進む

スズラン・フデリンドウ・ミヤマエンレイソウ・ヒメイチゲ

ピンクがかったミヤマエンレイソウ

10:45 一望台(3合目)あたりの羊蹄山

そして有珠山

6合目の少し上の「ガンバレ岩」を過ぎる。帰りは反対側に「マタキテネ」

11:35 7合目「いっぷく広場」に到着

「いっぷく広場」から南東隣りの稀府岳

これから向かう前紋別岳方向

チシマフウロ・キジムシロ・ノウゴウイチゴ・ミヤマアズマギク

前紋別岳に向かう

エゾコザクラ

ミヤマオダマキ・ナツトウダイ・エゾアオイスミレ?・ハクサンチドリ

前紋別岳への最後の登り

12:15 前紋別岳から羊蹄山

紋別岳本峰を望む

シラネアオイの群落

白花のシラネアオイ

本峰への最後の登り

12:45 頂上から昆布岳と遠く目国内岳

左遠くに徳舜瞥山とホロホロ山

頂上 全体集合

頂上 全体集合 その2

昼食後 13:15下山開始 15:15登山口到着 暑さにバテましたが、沢山の花と眺望に恵まれた1日でした。