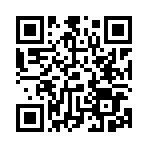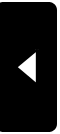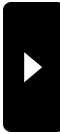2019年04月29日
4月28日 元山・笹山・八幡岳
江差の元山・笹山・八幡岳は当会では2017年5月3日以来2年ぶりだった。その時の模様はこちらをご覧ください。江差の道の駅で車を減らして登山口へ向かう。車7台総勢32名。準備を済ませ,快晴の中,9時前に出発。
道の駅から見えた白水岳・冷水岳・遊楽部岳はまだ雪が白い。

準備中の模様。

登り初めはトドマツ植林地の急登。

早速テングスミレ・カタクリ・キクザキイチゲ・オオバキスミレが迎えてくれる。




元山・笹山の分岐を過ぎて10時前に元山への最後の急登を登る。

ここではいつもイワナシが見られる。

元山からしばし展望を楽しむ。先ずは大千軒岳(右)と七ツ岳(左),次に七ツ岳クローズアップ,これから向かう笹山,北北東に乙部岳。




笹山へ向かう前にここで全体写真。

一旦分岐まで下り,笹山へのアップダウンが始まる。ここではエゾエンゴサクが見られた。

笹山への登りが始まり,振り返ると元山がやや下に見えて来る。


笹山への最後の登りでは江差のIさんご夫婦と当会元会員のImさんご夫婦が笹刈をしてくれていました。毎年されてくれているそうで,感謝感謝です。
12時前に笹山到着。ここで昼ご飯とする。

32人中14名が八幡岳を目指し,12時20分に出発。居残り組18名は周辺を散策したり,昼寝をしたりして八幡岳組を待った。ガールズトークもあり。

八幡岳への稜線にはまだ雪も見られたが,登山道はそれほど荒れていなかったようだ。

ほぼ一時間で八幡岳到着。ここの三角点は北海道最初の一等三角点のうちの一つだそうだ。


頂上から駒ヶ岳(左)と焼木尻岳(右)も見られた。


最後に,開いたカタクリをパチリ。

15時前に下山終了。帰り支度と挨拶を済ませ,車毎に解散した。風がやや冷たく,歩いていないと寒いくらいだったが,初春の山をのんびり楽しむことができた。
道の駅から見えた白水岳・冷水岳・遊楽部岳はまだ雪が白い。

準備中の模様。

登り初めはトドマツ植林地の急登。

早速テングスミレ・カタクリ・キクザキイチゲ・オオバキスミレが迎えてくれる。




元山・笹山の分岐を過ぎて10時前に元山への最後の急登を登る。

ここではいつもイワナシが見られる。

元山からしばし展望を楽しむ。先ずは大千軒岳(右)と七ツ岳(左),次に七ツ岳クローズアップ,これから向かう笹山,北北東に乙部岳。




笹山へ向かう前にここで全体写真。

一旦分岐まで下り,笹山へのアップダウンが始まる。ここではエゾエンゴサクが見られた。

笹山への登りが始まり,振り返ると元山がやや下に見えて来る。


笹山への最後の登りでは江差のIさんご夫婦と当会元会員のImさんご夫婦が笹刈をしてくれていました。毎年されてくれているそうで,感謝感謝です。
12時前に笹山到着。ここで昼ご飯とする。

32人中14名が八幡岳を目指し,12時20分に出発。居残り組18名は周辺を散策したり,昼寝をしたりして八幡岳組を待った。ガールズトークもあり。

八幡岳への稜線にはまだ雪も見られたが,登山道はそれほど荒れていなかったようだ。

ほぼ一時間で八幡岳到着。ここの三角点は北海道最初の一等三角点のうちの一つだそうだ。


頂上から駒ヶ岳(左)と焼木尻岳(右)も見られた。


最後に,開いたカタクリをパチリ。

15時前に下山終了。帰り支度と挨拶を済ませ,車毎に解散した。風がやや冷たく,歩いていないと寒いくらいだったが,初春の山をのんびり楽しむことができた。
2019年04月23日
4月21日(日) 太鼓山~俄虫沢
4月の自然部山行は、春到来を告げる花々が満喫できる太鼓山(171m)から俄虫沢をゆったりと辿った。参加は23名(フリー参加3名を含む)。
この時期本来の気温で、気持ち良い青空が広がる中を9時35分に出発。

先ずは地味なオクノカンスゲ(奥の寒菅)から。

キクザキイチゲ(菊咲一華)は、この時期の常連メンバー。花の咲き始めは、少し色の付いた個体も…。


これも常連のカタクリ(片栗)は、場所によって一面の群落を形成している。

他のスミレに比べて距(花の萼や花冠の基部近くから突出した部分)が長いことから、ナガハシスミレ(長嘴菫)と名付けられた。別名のテングスミレ(天狗菫)も同じような意味で、長い距を天狗の鼻に見立てたもの。

エゾエンゴサク(蝦夷延胡索)は淡い青色の可憐な花が特徴だが、色は個体によって少しずつ異なる。空色、少し濃い青色、二色混合…。右下は、葉が細いホソバエゾエンゴサク。

エンレイソウ(延齢草)も主役。この辺りには「黒実」が多いようだが、たまに「白実」も…。


途中で立ち止まりながら、山野草や樹木、岩石の実物を前にして、詳しいメンバーから解説を聞く「自然部」山行のひとこま。

ヒトリシズカ(一人静)。別の場所では、これが何十人も…。

フキ(蕗、苳など)は雄株と雌株を分けることで、自家受粉を巧みに避けている。雄株(右)の花は花粉のためか黄色っぽく見えるのに対し、雌株(左)の花は白く見える。
![フキの雌株[左]と雄株[右] フキの雌株[左]と雄株[右]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190421-L%E5%A4%AA%E9%BC%93%E5%B1%B1k%E4%BF%84%E8%99%AB%E6%B2%A2k%E3%83%95%E3%82%AD%E3%81%AE%E9%9B%8C%E6%A0%AA%5B%E5%B7%A6%5D%E3%81%A8%E9%9B%84%E6%A0%AAk.jpg)
キブシ(木五倍子)は、北海道西南部から南の地方に分布する。名前は、実が染料に使われるヌルデの五倍子(ブシ)の代用になったことによる。

センボンヤリ(千本槍)の花を見かけた。春と秋に2回花を付けるが、秋の花は蕾のまま開かずに茶色い穂先になり、これが大名行列の毛槍に似ることが名前の由来。

可憐なフデリンドウ(筆竜胆)も…。

太鼓山の頂上で、最初の全体写真を撮る。前列向かって左から二人目のAtさんが持つ岩石のうち、左手のチャートは、堆積岩の一種。主成分は二酸化ケイ素(石英)で、石英質の骨格を持った海生浮遊性原生動物の一種である放散虫の化石が海底に堆積・密集してできた。断面をルーペで見ると、放散虫の殻が点状に見えるものもある。右手の珪岩(けいがん)は、チャートや珪質砂岩が地中深くで熱による変成を受けた変成岩。いずれも太鼓山を形成する代表的な岩石である(Ttさんの解説による)。

俄虫沢に向かう途中で見かけたスミレサイシン(菫細辛)は、北海道西部~山口県までの日本海側のあまり高くない山地が主体で、半日陰の落葉樹林下などを好む多年草。葉はハート形で先が尖る。ふつう、花期には写真下のように縮れていることが多い。

登山道から少し離れた樹木の幹に開けられたクマゲラの食痕。幹の中に巣くう蟻を食餌とするために掘ったもので、縦に長い矩形をしているのが特徴。

俄虫沢に降り立つと、これまでに見られた花のほか、キバナノアマナ(黄花の甘菜)やフクジュソウ(福寿草)の黄色も目についた。


沢の斜面は、まさに百花繚乱…。

そして、俄虫沢の主役であるエゾノリュウキンカ(蝦夷立金花)の群落が広がる。北海道ではヤチブキ(谷地蕗)とも呼ぶ。満開は、あと数日先のようだ。

流れの畔にミズバショウ(水芭蕉)。

俄虫沢のエゾノリュウキンカ群落を背景に、二度目の全体写真を撮る。

沢出口にある溜池堰堤の下でゆったりと昼食を摂り、駐車場に戻る。キタコブシ(北辛夷)の花は、ようやく開き始めた段階だった。

残雪をまとった乙部岳(1016.9m)。

いつもの畦道を通って、13時ちょうど駐車場にゴール。

太鼓山から俄虫沢を辿って3時間25分(昼食35分を含む)、いつにも増してゆったりと自然に親しむことができた。駐車場で全体の挨拶を済ませ、車毎に解散した。なお、車2台のメンバーは近くの「土橋自然観察教育林・レクの森」で、Ttさんによる追加の植物学習・鑑賞会となった。
この時期本来の気温で、気持ち良い青空が広がる中を9時35分に出発。

先ずは地味なオクノカンスゲ(奥の寒菅)から。

キクザキイチゲ(菊咲一華)は、この時期の常連メンバー。花の咲き始めは、少し色の付いた個体も…。


これも常連のカタクリ(片栗)は、場所によって一面の群落を形成している。

他のスミレに比べて距(花の萼や花冠の基部近くから突出した部分)が長いことから、ナガハシスミレ(長嘴菫)と名付けられた。別名のテングスミレ(天狗菫)も同じような意味で、長い距を天狗の鼻に見立てたもの。

エゾエンゴサク(蝦夷延胡索)は淡い青色の可憐な花が特徴だが、色は個体によって少しずつ異なる。空色、少し濃い青色、二色混合…。右下は、葉が細いホソバエゾエンゴサク。

エンレイソウ(延齢草)も主役。この辺りには「黒実」が多いようだが、たまに「白実」も…。


途中で立ち止まりながら、山野草や樹木、岩石の実物を前にして、詳しいメンバーから解説を聞く「自然部」山行のひとこま。

ヒトリシズカ(一人静)。別の場所では、これが何十人も…。

フキ(蕗、苳など)は雄株と雌株を分けることで、自家受粉を巧みに避けている。雄株(右)の花は花粉のためか黄色っぽく見えるのに対し、雌株(左)の花は白く見える。
![フキの雌株[左]と雄株[右] フキの雌株[左]と雄株[右]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190421-L%E5%A4%AA%E9%BC%93%E5%B1%B1k%E4%BF%84%E8%99%AB%E6%B2%A2k%E3%83%95%E3%82%AD%E3%81%AE%E9%9B%8C%E6%A0%AA%5B%E5%B7%A6%5D%E3%81%A8%E9%9B%84%E6%A0%AAk.jpg)
キブシ(木五倍子)は、北海道西南部から南の地方に分布する。名前は、実が染料に使われるヌルデの五倍子(ブシ)の代用になったことによる。

センボンヤリ(千本槍)の花を見かけた。春と秋に2回花を付けるが、秋の花は蕾のまま開かずに茶色い穂先になり、これが大名行列の毛槍に似ることが名前の由来。

可憐なフデリンドウ(筆竜胆)も…。

太鼓山の頂上で、最初の全体写真を撮る。前列向かって左から二人目のAtさんが持つ岩石のうち、左手のチャートは、堆積岩の一種。主成分は二酸化ケイ素(石英)で、石英質の骨格を持った海生浮遊性原生動物の一種である放散虫の化石が海底に堆積・密集してできた。断面をルーペで見ると、放散虫の殻が点状に見えるものもある。右手の珪岩(けいがん)は、チャートや珪質砂岩が地中深くで熱による変成を受けた変成岩。いずれも太鼓山を形成する代表的な岩石である(Ttさんの解説による)。

俄虫沢に向かう途中で見かけたスミレサイシン(菫細辛)は、北海道西部~山口県までの日本海側のあまり高くない山地が主体で、半日陰の落葉樹林下などを好む多年草。葉はハート形で先が尖る。ふつう、花期には写真下のように縮れていることが多い。

登山道から少し離れた樹木の幹に開けられたクマゲラの食痕。幹の中に巣くう蟻を食餌とするために掘ったもので、縦に長い矩形をしているのが特徴。

俄虫沢に降り立つと、これまでに見られた花のほか、キバナノアマナ(黄花の甘菜)やフクジュソウ(福寿草)の黄色も目についた。


沢の斜面は、まさに百花繚乱…。

そして、俄虫沢の主役であるエゾノリュウキンカ(蝦夷立金花)の群落が広がる。北海道ではヤチブキ(谷地蕗)とも呼ぶ。満開は、あと数日先のようだ。

流れの畔にミズバショウ(水芭蕉)。

俄虫沢のエゾノリュウキンカ群落を背景に、二度目の全体写真を撮る。

沢出口にある溜池堰堤の下でゆったりと昼食を摂り、駐車場に戻る。キタコブシ(北辛夷)の花は、ようやく開き始めた段階だった。

残雪をまとった乙部岳(1016.9m)。

いつもの畦道を通って、13時ちょうど駐車場にゴール。

太鼓山から俄虫沢を辿って3時間25分(昼食35分を含む)、いつにも増してゆったりと自然に親しむことができた。駐車場で全体の挨拶を済ませ、車毎に解散した。なお、車2台のメンバーは近くの「土橋自然観察教育林・レクの森」で、Ttさんによる追加の植物学習・鑑賞会となった。
2019年04月15日
4月14日(日) 漁岳
漁岳(いざりだけ、1,317.2m)は支笏湖の北西方向、札幌市(南区)・恵庭市・千歳市の三重境界点に聳える。夏道はないが、札幌市に近くて山頂からの展望が素晴らしいことから、残雪期に山スキーやスノーシュー、つぼ足で登る人が多い。今回は当クラブ2年振りの登山で、参加は11名(初登山は9名)。
前日の宿泊地を、05時35分に車3台で出発。雲がやや多く霞んでいたが、支笏湖北岸道路から樽前山(1,041m)が四角形、風不死岳(1,102.3m)は三角形の特徴的な姿を見せていた。
![支笏湖道路から樽前山[左]&風不死岳[右] 支笏湖道路から樽前山[左]&風不死岳[右]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-A%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E6%94%AF%E7%AC%8F%E6%B9%96%E9%81%93%E8%B7%AF%E3%81%8B%E3%82%89%E6%A8%BD%E5%89%8D%E5%B1%B1%5B%E5%B7%A6%5Dk%E9%A2%A8%E4%B8%8D%E6%AD%BB%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%5Dk.jpg)
前方には端正な姿の恵庭岳(1,320m)と、右奥にたおやかな姿の漁岳。風が弱く、湖面は割合に穏やかだった。
![恵庭岳&漁岳[右奥] 恵庭岳&漁岳[右奥]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-B%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E6%81%B5%E5%BA%AD%E5%B2%B3k%E6%BC%81%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%E5%A5%A5%5Dk.jpg)
恵庭岳頂上部の岩峰も姿を見せている。

漁川林道入口で、函館から未明に到着して仮眠を取っていたTtさんと合流。出発準備を整え、リーダーから注意事項を伝達したあと、07時10分に出発。

歩くうちに雲がすっかりとれて、爽やかな青空が広がってきた。漁岳の稜線一角を仰ぎながら、林道を約2.6km辿る。

1時間5分で冬道ルート取付地点に到着(08時15分)。これからの本格的な登りに備えて、装備の具合を点検する。

取付地点の樹木に冬季ルートの標識が付けられていた。ここを08時20分に出発。

冬季ルートを辿って高度を稼いでいくと、右手に青空を背景にした1175m前衛峰と本峰が望めた。
![1175m前衛峰と本峰[右奥] 1175m前衛峰と本峰[右奥]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-H%E6%BC%81%E5%B2%B3k1175m%E5%89%8D%E8%A1%9B%E5%B3%B0%E3%81%A8%E6%9C%AC%E5%B3%B0%5B%E5%8F%B3%E5%A5%A5%5Dk.jpg)
恵庭・千歳市境界尾根のC890台地に上がると、左手に恵庭岳が聳えている。二つの目立つ頂上岩峰が猫の耳のように見えることから、メンバーで勝手に「エニャー岳」と名付けてみた。

C900付近の気持ち良い雪面を登る。

C920付近まで登ると、左下にオコタンペ湖が俯瞰できた。

恵庭岳の左向こう(支笏湖の北岸)に位置する紋別岳(865.6m)も望めた。

C1050付近を登る。空はますます青く、春山の雰囲気に満ちてくる。ただし、西南西の風がやや強い。

恵庭岳を振り返ると、その姿がいっそう立派に見えていた。

ルート脇にあった木の枯れ枝がハート型になっていたので、恵庭岳の頂上岩峰を覗き見るように撮ってみた。

進行方向左手に、漁岳から南に繋がる稜線上の小漁岳(1,235.1m)。
![南に繋がる尾根上の小漁岳[右]方面 南に繋がる尾根上の小漁岳[右]方面](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-P%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E5%8D%97%E3%81%AB%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%8B%E5%B0%BE%E6%A0%B9%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%B0%8F%E6%BC%81%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%5D%E6%96%B9%E9%9D%A2k.jpg)
1175m前衛峰の南側山腹をトラバースして、本峰直下の最終コル(1,155m)に向かう。

最終コルから頂上まで、標高差160mほどの急登が待っている。25分ほどをかけて、ゆっくりと登り詰める。空の青と雪面の白が、辛さを和らげてくれる。

11時ちょうど、待望の山頂に到着。周囲の景色を眺め、個別に記念写真を撮り合った後、恒例の全体写真に納まる。最初の写真、向って左端・Atさんのピースサインに羊蹄山(1,898m)が挟まっている。2枚目写真、右端に無意根山(1,460.2m)、左から3人目・Yhさんの顔が羊蹄山と並んでいる。
![頂上集合①[左端Vサインで羊蹄山を挟む] 頂上集合①[左端Vサインで羊蹄山を挟む]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-S%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E9%9B%86%E5%90%88%E2%91%A0%5B%E5%B7%A6%E7%AB%AFV%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E7%BE%8A%E8%B9%84%E5%B1%B1%E3%82%92%E6%8C%9F%E3%82%80%5Dk.jpg)
![頂上集合②[右端は無意根山] 頂上集合②[右端は無意根山]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-T%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E9%9B%86%E5%90%88%E2%91%A1%5B%E5%8F%B3%E7%AB%AF%E3%81%AF%E7%84%A1%E6%84%8F%E6%A0%B9%E5%B1%B1%5Dk.jpg)
山頂からの展望をどうぞ。先ず、南南西方向には、手前に小漁岳(1,235.1m)と左奥にホロホロ山(1,322.3m)・徳舜瞥山(1,309m)。
![山頂から小漁岳とホロホロ・徳舜[左奥] 山頂から小漁岳とホロホロ・徳舜[左奥]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-U%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E5%B1%B1%E9%A0%82%E3%81%8B%E3%82%89%E5%B0%8F%E6%BC%81%E5%B2%B3%E3%81%A8%E3%83%9B%E3%83%AD%E3%83%9B%E3%83%AD%EF%BD%A5%E5%BE%B3%E8%88%9C%5B%E5%B7%A6%E5%A5%A5%5Dk.jpg)
[以下3枚は、なぜかモノクロに…]西から北西には、左に羊蹄山(1,898m)、右に無意根山(1,460.2m)。
![山頂から羊蹄山[左]&無意根山[右]:モノクロ 山頂から羊蹄山[左]&無意根山[右]:モノクロ](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-V%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E5%B1%B1%E9%A0%82%E3%81%8B%E3%82%89%E7%BE%8A%E8%B9%84%E5%B1%B1%5B%E5%B7%A6%5Dk%E7%84%A1%E6%84%8F%E6%A0%B9%E5%B1%B1%5B%E5%8F%B3%5D%EF%BC%9A%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%82%AF%E3%83%ADk.jpg)
中央に羊蹄山と左端に尻別岳(1,107.3m)の「ノミの夫婦」の姿(ズーム)。

北には、中央奥に空沼岳(1,251m)。
![山頂から空沼岳[中]方面:モノクロ 山頂から空沼岳[中]方面:モノクロ](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-X%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E5%B1%B1%E9%A0%82%E3%81%8B%E3%82%89%E7%A9%BA%E6%B2%BC%E5%B2%B3%5B%E4%B8%AD%5D%E6%96%B9%E9%9D%A2%EF%BC%9A%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%82%AF%E3%83%ADk.jpg)
やや強い西風を避けて、頂上の東側に少し下がって昼食とする。11時40分に下山開始。山頂下の大斜面は、三々五々にシリセードで豪快に下る。中には「三回転半」などの「高度テクニック」を披露するメンバーも…。


登りと同様に、1175m前衛峰の山腹をトラバースし、恵庭岳を望みながら下る。

下山途中、登りで「♡マークに納まった恵庭岳岩峰」を撮影した展望の良い地点で、恵庭岳や支笏湖などを背景にして、皆さんの満足顔を写真に収めた。

冬道ルート取付地点に13時10分着・15分発、林道入口には14時ちょうどに到着して下山終了。
支笏湖西岸のM温泉旅館で入浴し、八雲町中心部手前のキッチン&カフェで夕食を摂って帰宅した。
すっきりした青空と素晴らしい展望に恵まれて、初登頂の皆さんは大満足の様子であった。
前日の宿泊地を、05時35分に車3台で出発。雲がやや多く霞んでいたが、支笏湖北岸道路から樽前山(1,041m)が四角形、風不死岳(1,102.3m)は三角形の特徴的な姿を見せていた。
![支笏湖道路から樽前山[左]&風不死岳[右] 支笏湖道路から樽前山[左]&風不死岳[右]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-A%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E6%94%AF%E7%AC%8F%E6%B9%96%E9%81%93%E8%B7%AF%E3%81%8B%E3%82%89%E6%A8%BD%E5%89%8D%E5%B1%B1%5B%E5%B7%A6%5Dk%E9%A2%A8%E4%B8%8D%E6%AD%BB%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%5Dk.jpg)
前方には端正な姿の恵庭岳(1,320m)と、右奥にたおやかな姿の漁岳。風が弱く、湖面は割合に穏やかだった。
![恵庭岳&漁岳[右奥] 恵庭岳&漁岳[右奥]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-B%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E6%81%B5%E5%BA%AD%E5%B2%B3k%E6%BC%81%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%E5%A5%A5%5Dk.jpg)
恵庭岳頂上部の岩峰も姿を見せている。

漁川林道入口で、函館から未明に到着して仮眠を取っていたTtさんと合流。出発準備を整え、リーダーから注意事項を伝達したあと、07時10分に出発。

歩くうちに雲がすっかりとれて、爽やかな青空が広がってきた。漁岳の稜線一角を仰ぎながら、林道を約2.6km辿る。

1時間5分で冬道ルート取付地点に到着(08時15分)。これからの本格的な登りに備えて、装備の具合を点検する。

取付地点の樹木に冬季ルートの標識が付けられていた。ここを08時20分に出発。

冬季ルートを辿って高度を稼いでいくと、右手に青空を背景にした1175m前衛峰と本峰が望めた。
![1175m前衛峰と本峰[右奥] 1175m前衛峰と本峰[右奥]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-H%E6%BC%81%E5%B2%B3k1175m%E5%89%8D%E8%A1%9B%E5%B3%B0%E3%81%A8%E6%9C%AC%E5%B3%B0%5B%E5%8F%B3%E5%A5%A5%5Dk.jpg)
恵庭・千歳市境界尾根のC890台地に上がると、左手に恵庭岳が聳えている。二つの目立つ頂上岩峰が猫の耳のように見えることから、メンバーで勝手に「エニャー岳」と名付けてみた。

C900付近の気持ち良い雪面を登る。

C920付近まで登ると、左下にオコタンペ湖が俯瞰できた。

恵庭岳の左向こう(支笏湖の北岸)に位置する紋別岳(865.6m)も望めた。

C1050付近を登る。空はますます青く、春山の雰囲気に満ちてくる。ただし、西南西の風がやや強い。

恵庭岳を振り返ると、その姿がいっそう立派に見えていた。

ルート脇にあった木の枯れ枝がハート型になっていたので、恵庭岳の頂上岩峰を覗き見るように撮ってみた。

進行方向左手に、漁岳から南に繋がる稜線上の小漁岳(1,235.1m)。
![南に繋がる尾根上の小漁岳[右]方面 南に繋がる尾根上の小漁岳[右]方面](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-P%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E5%8D%97%E3%81%AB%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%8B%E5%B0%BE%E6%A0%B9%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%B0%8F%E6%BC%81%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%5D%E6%96%B9%E9%9D%A2k.jpg)
1175m前衛峰の南側山腹をトラバースして、本峰直下の最終コル(1,155m)に向かう。

最終コルから頂上まで、標高差160mほどの急登が待っている。25分ほどをかけて、ゆっくりと登り詰める。空の青と雪面の白が、辛さを和らげてくれる。

11時ちょうど、待望の山頂に到着。周囲の景色を眺め、個別に記念写真を撮り合った後、恒例の全体写真に納まる。最初の写真、向って左端・Atさんのピースサインに羊蹄山(1,898m)が挟まっている。2枚目写真、右端に無意根山(1,460.2m)、左から3人目・Yhさんの顔が羊蹄山と並んでいる。
![頂上集合①[左端Vサインで羊蹄山を挟む] 頂上集合①[左端Vサインで羊蹄山を挟む]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-S%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E9%9B%86%E5%90%88%E2%91%A0%5B%E5%B7%A6%E7%AB%AFV%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E7%BE%8A%E8%B9%84%E5%B1%B1%E3%82%92%E6%8C%9F%E3%82%80%5Dk.jpg)
![頂上集合②[右端は無意根山] 頂上集合②[右端は無意根山]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-T%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E9%9B%86%E5%90%88%E2%91%A1%5B%E5%8F%B3%E7%AB%AF%E3%81%AF%E7%84%A1%E6%84%8F%E6%A0%B9%E5%B1%B1%5Dk.jpg)
山頂からの展望をどうぞ。先ず、南南西方向には、手前に小漁岳(1,235.1m)と左奥にホロホロ山(1,322.3m)・徳舜瞥山(1,309m)。
![山頂から小漁岳とホロホロ・徳舜[左奥] 山頂から小漁岳とホロホロ・徳舜[左奥]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-U%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E5%B1%B1%E9%A0%82%E3%81%8B%E3%82%89%E5%B0%8F%E6%BC%81%E5%B2%B3%E3%81%A8%E3%83%9B%E3%83%AD%E3%83%9B%E3%83%AD%EF%BD%A5%E5%BE%B3%E8%88%9C%5B%E5%B7%A6%E5%A5%A5%5Dk.jpg)
[以下3枚は、なぜかモノクロに…]西から北西には、左に羊蹄山(1,898m)、右に無意根山(1,460.2m)。
![山頂から羊蹄山[左]&無意根山[右]:モノクロ 山頂から羊蹄山[左]&無意根山[右]:モノクロ](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-V%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E5%B1%B1%E9%A0%82%E3%81%8B%E3%82%89%E7%BE%8A%E8%B9%84%E5%B1%B1%5B%E5%B7%A6%5Dk%E7%84%A1%E6%84%8F%E6%A0%B9%E5%B1%B1%5B%E5%8F%B3%5D%EF%BC%9A%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%82%AF%E3%83%ADk.jpg)
中央に羊蹄山と左端に尻別岳(1,107.3m)の「ノミの夫婦」の姿(ズーム)。

北には、中央奥に空沼岳(1,251m)。
![山頂から空沼岳[中]方面:モノクロ 山頂から空沼岳[中]方面:モノクロ](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190414-X%E6%BC%81%E5%B2%B3k%E5%B1%B1%E9%A0%82%E3%81%8B%E3%82%89%E7%A9%BA%E6%B2%BC%E5%B2%B3%5B%E4%B8%AD%5D%E6%96%B9%E9%9D%A2%EF%BC%9A%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%82%AF%E3%83%ADk.jpg)
やや強い西風を避けて、頂上の東側に少し下がって昼食とする。11時40分に下山開始。山頂下の大斜面は、三々五々にシリセードで豪快に下る。中には「三回転半」などの「高度テクニック」を披露するメンバーも…。


登りと同様に、1175m前衛峰の山腹をトラバースし、恵庭岳を望みながら下る。

下山途中、登りで「♡マークに納まった恵庭岳岩峰」を撮影した展望の良い地点で、恵庭岳や支笏湖などを背景にして、皆さんの満足顔を写真に収めた。

冬道ルート取付地点に13時10分着・15分発、林道入口には14時ちょうどに到着して下山終了。
支笏湖西岸のM温泉旅館で入浴し、八雲町中心部手前のキッチン&カフェで夕食を摂って帰宅した。
すっきりした青空と素晴らしい展望に恵まれて、初登頂の皆さんは大満足の様子であった。
2019年04月14日
4月14日 恵山
この日もう一つの山行(漁岳)に参加しなかった函館組のために恵山に行って来た。この時期の恵山は私の知る限りでは初めてだ。ルートは「ホテル恵風(cape)」からの登り2時間のルート。天気は快晴。参加者は11名。「恵風」駐車場から9時45分に出発。
林間コースを過ぎ一度林道へ出て登山口へ向かう。

C240m辺りで視界が開ける。

C365で登山道に残雪が現れ,ツルリンドウが色鮮やかに見えた。


権現堂コースに入るといつものことだが奇岩が目に入る。Iさん曰く「岩のシャチホコ」。

12時6分頂上着。昼食前に全体写真。この日は飛行機雲がよく見えた。中には飛行機雲の交差も。


30分ほど昼食を摂り,12時40分下山開始。下山途中,恵山の一部と津軽海峡がきれいに見えた。

さらにキタキツネが姿を見せてくれた。



14時過ぎに登山口まで下りて来た。

14時27分下山終了。挨拶を済ませ,車毎に解散した。
林間コースを過ぎ一度林道へ出て登山口へ向かう。

C240m辺りで視界が開ける。

C365で登山道に残雪が現れ,ツルリンドウが色鮮やかに見えた。


権現堂コースに入るといつものことだが奇岩が目に入る。Iさん曰く「岩のシャチホコ」。

12時6分頂上着。昼食前に全体写真。この日は飛行機雲がよく見えた。中には飛行機雲の交差も。


30分ほど昼食を摂り,12時40分下山開始。下山途中,恵山の一部と津軽海峡がきれいに見えた。

さらにキタキツネが姿を見せてくれた。



14時過ぎに登山口まで下りて来た。

14時27分下山終了。挨拶を済ませ,車毎に解散した。
2019年04月08日
4/7(日) 当別丸山(早春トレッキング)
例年4月第一日曜に「北斗市自然に親しむ会」主催の早春トレッキングが「当別丸山」で行われ、函館山楽クラブは一般登山者のサポートに当たっている。当日は朝からミゾレ混じりの冷たい雨が止まず、中止か迷う天候だったが昼前に回復する予報を信じ決行、全部で38人が参加した。
主催者による説明と注意事項伝達。

墓地の前を通過し牧草地を回り込む。雨は止まない。

山頂方面は雲の中、はたして天候は回復するか?

227段の階段を上ると、ルルド洞窟のマリア像が登山者を迎えてくれる。

展望台から見える修道院と敷地、雨が止んできた。

展望台から見える函館山はいつも見る姿の裏側なので新鮮な感じ。右後方に見えるのは汐首岬。

尾根の中間部は雪と笹が混交し、所々で夏道が顔を出していた。

最後尾を歩く当会のリーダーが下山時に一般登山者が安全に下れるよう、急傾斜の雪道にロープをFIX。

登山中に樹林の合間から見える函館山と津軽海峡。木々が芽吹き始めると登山道からは見えづらくなるので、4月はベストシーズン。

山頂で30分休憩し昼食、下山は滑りやすく転ぶと怪我になるのでリーダーが注意事項を伝える。

下り始めは急斜面が続くので慎重に。

FIXロープを頼りに下る参加者。


この山で一番先に咲くのは「ナニワズ」の花。落葉小低木で、この花が咲くと春到来と感じる。

「シロキツネノサカズキモドキ」は、雪が溶けたばかりの早春に生えるキノコだとか。

雨降る中のスタートだったが天候はどんどん回復、山頂では青空も見え参加者の笑顔が広がった。体調不良になったり大きく遅れる参加者が出なかったことが何よりだった。
主催者による説明と注意事項伝達。

墓地の前を通過し牧草地を回り込む。雨は止まない。

山頂方面は雲の中、はたして天候は回復するか?

227段の階段を上ると、ルルド洞窟のマリア像が登山者を迎えてくれる。

展望台から見える修道院と敷地、雨が止んできた。

展望台から見える函館山はいつも見る姿の裏側なので新鮮な感じ。右後方に見えるのは汐首岬。

尾根の中間部は雪と笹が混交し、所々で夏道が顔を出していた。

最後尾を歩く当会のリーダーが下山時に一般登山者が安全に下れるよう、急傾斜の雪道にロープをFIX。

登山中に樹林の合間から見える函館山と津軽海峡。木々が芽吹き始めると登山道からは見えづらくなるので、4月はベストシーズン。

山頂で30分休憩し昼食、下山は滑りやすく転ぶと怪我になるのでリーダーが注意事項を伝える。

下り始めは急斜面が続くので慎重に。

FIXロープを頼りに下る参加者。


この山で一番先に咲くのは「ナニワズ」の花。落葉小低木で、この花が咲くと春到来と感じる。

「シロキツネノサカズキモドキ」は、雪が溶けたばかりの早春に生えるキノコだとか。

雨降る中のスタートだったが天候はどんどん回復、山頂では青空も見え参加者の笑顔が広がった。体調不良になったり大きく遅れる参加者が出なかったことが何よりだった。