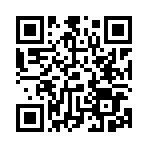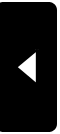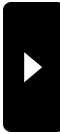2019年04月06日
函館山楽クラブ 2019年度 総会
4月3日(水)19:00~ 北斗市文化センター『かなで~る』において今年度の総会が開催されました。議長S氏の滑らかな進行で、自然部も含め平成30年度の山行活動(年60回計画され、うち悪天候のため7・8・9月を中心に11回の中止がありました。)と会計決算・監査の報告がなされ、承認されました。引き続き今年度の山行活動計画(アンケートをもとに意見・要望が出されました。)と予算案が出され熊スプレーの補充・冬山スコップ・携帯コッヘル・テントなどの装備品の購入が承認されました。その他 山行時の決め事・規約・役割分担など確認されました。新しい会員さんも入り、山を楽しむ『山楽クラブ』のスタートです。

4月の行事予定
当別丸山(北斗自然に親しむ会 早春トレッキング) 漁岳 恵山 太鼓山(厚沢部) 元山~笹山~八幡岳 袴腰岳

4月の行事予定
当別丸山(北斗自然に親しむ会 早春トレッキング) 漁岳 恵山 太鼓山(厚沢部) 元山~笹山~八幡岳 袴腰岳

2019年03月27日
3月24日 横津岳
自然部3月の山行は毎年恒例の横津岳樹氷観察。今年は雪が消えるのが早く,樹氷やスノーモンスターは期待できないと思っていたが,数日前から寒の戻りがあり,当日朝も雪だったため,まずまずの樹氷が見られた。さすがにスノーモンスターはなかったが,山はしっかり冬だった。ちょっと吹雪いたりされたが,思いのほか風も強くなく,時折青空も見え,山頂レーダーまで行くことができた。参加は16名。シニアやグランドシニアの回数券を利用して格安ゴンドラで山頂駅まで登り,スノーシューなどを装着して9時40分山頂駅を出発。
山頂駅の上にある高速リフト終点まで来たら駒ヶ岳がよく見えた。

東側を見下ろすと凛としたダケカンバが立っている。

10時半頃に1035ピーク脇を過ぎるとレーダーが見えて来た。

さらに30分歩くと随分大きく見えて来た。

もう少し歩いて後ろを振り返ると大沼全体と駒ヶ岳が視界に入った。空には黒雲。

程なく遠隔対空通信施設の対空受信所に到着。

11時半,頂上の航空路監視レーダーに到着。レーダードームには西側だけ雪が張り付いている。

開発局の無線中継所のアンテナにも少し雪がついているが,「氷の宮殿」には程遠い。

風を避けて昼食を摂る。その間に頂上からの展望を撮る。左から鹿部丸山,熊泊山,泣面山。

南側のレーダー群と烏帽子岳(右)・袴腰岳(左)。

うっすらと函館山も見えた。

昼食を済ませ,レーダードームを背景に全体写真。

12時に下山開始。1035ピーク東側,バックカントリースキーのきれいなスロープを見に少し寄り道し,登りでは避けた急斜面を一気に下りた(尻滑りも)。高速リフト手前まで来てもう一度全体写真を撮った。後ろにうっすらと駒ヶ岳。

13時18分下山終了。スノーシューなどを脱いでそれぞれゴンドラで下山し,ゴンドラ山麓駅で挨拶を済ませた上で車毎に解散した。朝はゴンドラが運行されるかさえ心配された天気だったが,頂上まで行けたのは幸運だった。みなさん十分に冬山を楽しめたと思う。
山頂駅の上にある高速リフト終点まで来たら駒ヶ岳がよく見えた。

東側を見下ろすと凛としたダケカンバが立っている。

10時半頃に1035ピーク脇を過ぎるとレーダーが見えて来た。

さらに30分歩くと随分大きく見えて来た。

もう少し歩いて後ろを振り返ると大沼全体と駒ヶ岳が視界に入った。空には黒雲。

程なく遠隔対空通信施設の対空受信所に到着。

11時半,頂上の航空路監視レーダーに到着。レーダードームには西側だけ雪が張り付いている。

開発局の無線中継所のアンテナにも少し雪がついているが,「氷の宮殿」には程遠い。

風を避けて昼食を摂る。その間に頂上からの展望を撮る。左から鹿部丸山,熊泊山,泣面山。

南側のレーダー群と烏帽子岳(右)・袴腰岳(左)。

うっすらと函館山も見えた。

昼食を済ませ,レーダードームを背景に全体写真。

12時に下山開始。1035ピーク東側,バックカントリースキーのきれいなスロープを見に少し寄り道し,登りでは避けた急斜面を一気に下りた(尻滑りも)。高速リフト手前まで来てもう一度全体写真を撮った。後ろにうっすらと駒ヶ岳。

13時18分下山終了。スノーシューなどを脱いでそれぞれゴンドラで下山し,ゴンドラ山麓駅で挨拶を済ませた上で車毎に解散した。朝はゴンドラが運行されるかさえ心配された天気だったが,頂上まで行けたのは幸運だった。みなさん十分に冬山を楽しめたと思う。
2019年03月18日
3月17日(日) 熊泊山
熊泊山(くまどまりやま、817.9m)は、函館市(旧・南茅部町)と鹿部町の市町境に位置している。登りの所要時間は2時間弱と短く、780mピークまで登った後は快適な尾根歩きと素晴らしい展望が楽しめる。参加は31名。
黒羽尻川の河口付近で車7台に乗り合わせ、林道に入る。道は除雪されていたが、登るにつれて路面の積雪が深くなった。C480付近の熊泊山取り付き地点では、スコップをフル動員して駐車スペースを確保した。「除雪で疲れたから帰ろうか」の冗談も出るなか、スノーシュー・わかんを装着し、リーダーから注意事項を伝達して10時10分に出発。

780mピークから北に延びる市町境尾根(以下「北尾根」という)の末端に取り付くため、樹林帯を西に向って進む。

北尾根末端のやや急な斜面を、ジグを切って登る。ここ一週間の降雪により、新雪が20cm(上部では30cm)ほど積もっていた。

少し緩やかになったところで、樹林越しに駒ヶ岳を眺めながら一息。

北尾根上部の東側は雪庇が発達している。右手の樹林帯からあまり外れないよう、慎重にルートを見定めて登る。

北尾根の細くて急な箇所を過ぎて、間もなく780mピークに到着するところ。

780mピークで南方の展望が一気に開ける。山々を同定しながら休憩。

頂上に向かう明るい稜線を進む。心配した雪庇はあまり発達していなかったが、最近は稜線上に灌木が目立つようになり、通過に煩わしい箇所もあった。

稜線漫歩はわずか450mの距離だが、楽しいひとときである。31人も歩くと「高速道路」ができ上がる。

この頂上を初めて踏むメンバーを先頭にして、12時少し前、雪庇が張り出している頂上に到着。

頂上から横津岳方面を眺めて歓声を上げるメンバーも…。

常呂川を挟んだ東に鹿部丸山(909.2m)。最高点は、平坦に見える山頂部の右端にある。

横津岳から烏帽子岳、袴腰岳に至る横津連峰を望む。

熊泊山から烏帽子岳に繋がる、やや複雑な地形の稜線。これも、函館市(旧・南茅部町)と鹿部町の市町境を成している。
![烏帽子岳[右の雪山]に続く市町境稜線 烏帽子岳[右の雪山]に続く市町境稜線](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190317-N%E7%86%8A%E6%B3%8A%E5%B1%B1k%E7%83%8F%E5%B8%BD%E5%AD%90%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%E3%81%AE%E9%9B%AA%E5%B1%B1%5D%E3%81%AB%E7%B6%9A%E3%81%8F%E5%B8%82%E7%94%BA%E5%A2%83%E7%A8%9C%E7%B7%9Ak.jpg)
南南東には三森山(842.1m)。馴れ親しんだ三つのピークを持つ姿には見えない。

さらに、東には泣面山(834.9m)。右の黒っぽい山は803mピーク。この右奥に古部丸山が少しの間、見えていた。

横津連峰を背景にして、恒例の頂上集合写真。

西風が当たらない窪地で、ランチタイムとする。


12時35分に山頂を出発し、13時25分に下山終了。駐車場所で挨拶を済ませ、入浴は車毎として解散した。780mピークまでの登りは思わぬ深雪で、先頭グループはラッセルとルート選びに若干苦労したが、その後は快適な尾根歩きが楽しめた。まずまずの天気と展望に恵まれた一日であった。
なお、参加者が多くてリーダーの眼が届かないこともあるため、男性のOkさんとSyさんには隊列の中で前後のメンバーに目配りやサポートをしていただいた。また、女性のYhさんとMsさんには、先頭グループでラッセルをしていただいた。ありがとうございました。
黒羽尻川の河口付近で車7台に乗り合わせ、林道に入る。道は除雪されていたが、登るにつれて路面の積雪が深くなった。C480付近の熊泊山取り付き地点では、スコップをフル動員して駐車スペースを確保した。「除雪で疲れたから帰ろうか」の冗談も出るなか、スノーシュー・わかんを装着し、リーダーから注意事項を伝達して10時10分に出発。

780mピークから北に延びる市町境尾根(以下「北尾根」という)の末端に取り付くため、樹林帯を西に向って進む。

北尾根末端のやや急な斜面を、ジグを切って登る。ここ一週間の降雪により、新雪が20cm(上部では30cm)ほど積もっていた。

少し緩やかになったところで、樹林越しに駒ヶ岳を眺めながら一息。

北尾根上部の東側は雪庇が発達している。右手の樹林帯からあまり外れないよう、慎重にルートを見定めて登る。

北尾根の細くて急な箇所を過ぎて、間もなく780mピークに到着するところ。

780mピークで南方の展望が一気に開ける。山々を同定しながら休憩。

頂上に向かう明るい稜線を進む。心配した雪庇はあまり発達していなかったが、最近は稜線上に灌木が目立つようになり、通過に煩わしい箇所もあった。

稜線漫歩はわずか450mの距離だが、楽しいひとときである。31人も歩くと「高速道路」ができ上がる。

この頂上を初めて踏むメンバーを先頭にして、12時少し前、雪庇が張り出している頂上に到着。

頂上から横津岳方面を眺めて歓声を上げるメンバーも…。

常呂川を挟んだ東に鹿部丸山(909.2m)。最高点は、平坦に見える山頂部の右端にある。

横津岳から烏帽子岳、袴腰岳に至る横津連峰を望む。

熊泊山から烏帽子岳に繋がる、やや複雑な地形の稜線。これも、函館市(旧・南茅部町)と鹿部町の市町境を成している。
![烏帽子岳[右の雪山]に続く市町境稜線 烏帽子岳[右の雪山]に続く市町境稜線](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190317-N%E7%86%8A%E6%B3%8A%E5%B1%B1k%E7%83%8F%E5%B8%BD%E5%AD%90%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%E3%81%AE%E9%9B%AA%E5%B1%B1%5D%E3%81%AB%E7%B6%9A%E3%81%8F%E5%B8%82%E7%94%BA%E5%A2%83%E7%A8%9C%E7%B7%9Ak.jpg)
南南東には三森山(842.1m)。馴れ親しんだ三つのピークを持つ姿には見えない。

さらに、東には泣面山(834.9m)。右の黒っぽい山は803mピーク。この右奥に古部丸山が少しの間、見えていた。

横津連峰を背景にして、恒例の頂上集合写真。

西風が当たらない窪地で、ランチタイムとする。


12時35分に山頂を出発し、13時25分に下山終了。駐車場所で挨拶を済ませ、入浴は車毎として解散した。780mピークまでの登りは思わぬ深雪で、先頭グループはラッセルとルート選びに若干苦労したが、その後は快適な尾根歩きが楽しめた。まずまずの天気と展望に恵まれた一日であった。
なお、参加者が多くてリーダーの眼が届かないこともあるため、男性のOkさんとSyさんには隊列の中で前後のメンバーに目配りやサポートをしていただいた。また、女性のYhさんとMsさんには、先頭グループでラッセルをしていただいた。ありがとうございました。
2019年03月11日
3月10日(日) 設計山
設計山(もっけやま、701.5m)は、国道227号線・中山トンネルの南東に聳える一等三角点の独立峰で、展望が良い。「もっけ」は、アイヌ語の「モ・ケ(小さい場所を占める山)」からきているらしい。「設計」の字を充てたのは、この山が北海道における近代的な地籍調査のスタート地点でもあり、その名残りが山名として残ったと言われる。参加は24名(フリー1名を含む)。なお、積雪が多かった前回(2018年4月8日)の様子は、こちらをご覧ください。
中山トンネルの北斗市側入口手前の駐車場に車を置き、道路反対側の雪面に上がってスノーシュー・わかんを装着する。リーダーから注意事項を伝達し、9時10分に出発。

天気は快晴。大野川源流部に沿う林道を辿っていくと、柔らかい日差しと弱い風のため暖かく、春到来を感じる。アウターを脱いで歩くメンバーも。

斜面下の林道脇に、小さいながら春の使者「雪まくり」が転がっていた。

林道のC400付近で休憩したのち、南に延びる尾根に取り付く。

尾根のC460付近で見かけた雪の造形。

C500付近で見かけた「サルオガセ」と思われる植物。先週の焼木尻岳で見つけた、きのこの菌糸が束になって発達した「山姥の髪の毛」という面白い名前の植物も話題になった。

C510の台地状尾根を行く。空は相変わらずの快晴だが、少し風が出てきたのでアウターを着る。

同じ場所から左手に、谷を挟んで前衛峰(左奥)が見えてきた。

ブナの大木の根元は「根明け(根開き)」が進んでいる。「コクワ(サルナシ)」と思われる太さ10cm以上の太い蔓が這い上がっていた。

尾根に取り付いてから距離830mほど進んだ所で尾根は東に向きを変え、緩やかなダウンアップを辿っていく。

やや急な登りの後、C590付近の樹間から乙部岳が美しい容姿を見せた。

C660付近まで登ると、右手(南側)に戸切地川をはさんで雷電山、遠くに桂岳が望めた。
![C660付近から雷電山[左]と桂岳[右奥] C660付近から雷電山[左]と桂岳[右奥]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190310-L%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%B1%B1kC660%E4%BB%98%E8%BF%91%E3%81%8B%E3%82%89%E9%9B%B7%E9%9B%BB%E5%B1%B1%5B%E5%B7%A6%5D%E3%81%A8%E6%A1%82%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%E5%A5%A5%5Dk_%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BB%98.jpg)
670m峰に上がると、正面に設計山の本峰(中央)が控えている。

頂上で発達した雪庇。到着したメンバーの姿が写っているが、それ以上左に行ってはならない。

同じ場所から東方向を眺める。北斗毛無山、木地挽高原、遠くに横津岳が望めた。
![頂上直前から毛無山[右]木地挽高原[左]横津岳[奥] 頂上直前から毛無山[右]木地挽高原[左]横津岳[奥]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190310-O%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%B1%B1k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E7%9B%B4%E5%89%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E6%AF%9B%E7%84%A1%E5%B1%B1%5B%E5%8F%B3%5D%E6%9C%A8%E5%9C%B0%E6%8C%BD%E9%AB%98%E5%8E%9F%5B%E5%B7%A6%5D%E6%A8%AA%E6%B4%A5%E5%B2%B3%5B%E5%A5%A5%5Dk_%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BB%98.jpg)
北方向には二股岳、中二股岳などと、遠くに駒ヶ岳。
![(同じく二股岳[右]駒ヶ岳[右奥]中二股岳[左] (同じく二股岳[右]駒ヶ岳[右奥]中二股岳[左]](//img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190310-P%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%B1%B1k%E5%90%8C%E3%81%98%E3%81%8F%E4%BA%8C%E8%82%A1%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%5D%E9%A7%92%E3%83%B6%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%E5%A5%A5%5D%E4%B8%AD%E4%BA%8C%E8%82%A1%E5%B2%B3%5B%E5%B7%A6%5Dk_%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BB%98.jpg)
二股岳と駒ヶ岳をアップでどうぞ。

11時20分、山頂に到着。雪庇が張り出している東側斜面には近づかず、西を向いてランチタイムとする。

山頂から北側の雪庇の様子。

同じく南側の様子。右の遠くに当別丸山(482.3m)が頭を出している。

会員だったJさん(故人)作の緑色山頂標識は、落下して雪の中に埋もれていたので、掘り出して再設置した。

恒例の全体写真を撮って、12時ちょうどに下山を開始。


13時30分に下山を終了。トンネル出口脇の駐車場で挨拶を済ませ、解散した。この日の函館市美原での最高気温は10.6℃と、二日連続で10℃を超える暖かい日和だった。そのため、ブロック雪崩や雪庇踏み抜きに十分注意を払って行動した。何事もなく無事に下山できたので、これが本当の「もっけ(勿怪)の幸い」か。暖かさを感じる春山気分と、素晴らしい展望に恵まれた一日であった。
中山トンネルの北斗市側入口手前の駐車場に車を置き、道路反対側の雪面に上がってスノーシュー・わかんを装着する。リーダーから注意事項を伝達し、9時10分に出発。

天気は快晴。大野川源流部に沿う林道を辿っていくと、柔らかい日差しと弱い風のため暖かく、春到来を感じる。アウターを脱いで歩くメンバーも。

斜面下の林道脇に、小さいながら春の使者「雪まくり」が転がっていた。

林道のC400付近で休憩したのち、南に延びる尾根に取り付く。

尾根のC460付近で見かけた雪の造形。

C500付近で見かけた「サルオガセ」と思われる植物。先週の焼木尻岳で見つけた、きのこの菌糸が束になって発達した「山姥の髪の毛」という面白い名前の植物も話題になった。

C510の台地状尾根を行く。空は相変わらずの快晴だが、少し風が出てきたのでアウターを着る。

同じ場所から左手に、谷を挟んで前衛峰(左奥)が見えてきた。

ブナの大木の根元は「根明け(根開き)」が進んでいる。「コクワ(サルナシ)」と思われる太さ10cm以上の太い蔓が這い上がっていた。

尾根に取り付いてから距離830mほど進んだ所で尾根は東に向きを変え、緩やかなダウンアップを辿っていく。

やや急な登りの後、C590付近の樹間から乙部岳が美しい容姿を見せた。

C660付近まで登ると、右手(南側)に戸切地川をはさんで雷電山、遠くに桂岳が望めた。
![C660付近から雷電山[左]と桂岳[右奥] C660付近から雷電山[左]と桂岳[右奥]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190310-L%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%B1%B1kC660%E4%BB%98%E8%BF%91%E3%81%8B%E3%82%89%E9%9B%B7%E9%9B%BB%E5%B1%B1%5B%E5%B7%A6%5D%E3%81%A8%E6%A1%82%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%E5%A5%A5%5Dk_%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BB%98.jpg)
670m峰に上がると、正面に設計山の本峰(中央)が控えている。

頂上で発達した雪庇。到着したメンバーの姿が写っているが、それ以上左に行ってはならない。
同じ場所から東方向を眺める。北斗毛無山、木地挽高原、遠くに横津岳が望めた。
![頂上直前から毛無山[右]木地挽高原[左]横津岳[奥] 頂上直前から毛無山[右]木地挽高原[左]横津岳[奥]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190310-O%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%B1%B1k%E9%A0%82%E4%B8%8A%E7%9B%B4%E5%89%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E6%AF%9B%E7%84%A1%E5%B1%B1%5B%E5%8F%B3%5D%E6%9C%A8%E5%9C%B0%E6%8C%BD%E9%AB%98%E5%8E%9F%5B%E5%B7%A6%5D%E6%A8%AA%E6%B4%A5%E5%B2%B3%5B%E5%A5%A5%5Dk_%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BB%98.jpg)
北方向には二股岳、中二股岳などと、遠くに駒ヶ岳。
![(同じく二股岳[右]駒ヶ岳[右奥]中二股岳[左] (同じく二股岳[右]駒ヶ岳[右奥]中二股岳[左]](http://img01.naturum.ne.jp/usr/s/a/n/sangakuclub/20190310-P%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%B1%B1k%E5%90%8C%E3%81%98%E3%81%8F%E4%BA%8C%E8%82%A1%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%5D%E9%A7%92%E3%83%B6%E5%B2%B3%5B%E5%8F%B3%E5%A5%A5%5D%E4%B8%AD%E4%BA%8C%E8%82%A1%E5%B2%B3%5B%E5%B7%A6%5Dk_%E5%B1%B1%E5%90%8D%E4%BB%98.jpg)
二股岳と駒ヶ岳をアップでどうぞ。

11時20分、山頂に到着。雪庇が張り出している東側斜面には近づかず、西を向いてランチタイムとする。

山頂から北側の雪庇の様子。

同じく南側の様子。右の遠くに当別丸山(482.3m)が頭を出している。

会員だったJさん(故人)作の緑色山頂標識は、落下して雪の中に埋もれていたので、掘り出して再設置した。

恒例の全体写真を撮って、12時ちょうどに下山を開始。


13時30分に下山を終了。トンネル出口脇の駐車場で挨拶を済ませ、解散した。この日の函館市美原での最高気温は10.6℃と、二日連続で10℃を超える暖かい日和だった。そのため、ブロック雪崩や雪庇踏み抜きに十分注意を払って行動した。何事もなく無事に下山できたので、これが本当の「もっけ(勿怪)の幸い」か。暖かさを感じる春山気分と、素晴らしい展望に恵まれた一日であった。
2019年03月07日
3月6日 3月例会
函館の積雪がゼロになり、日当たりの良いところでは福寿草の開花もちらほらみられるようになった。春山シーズンが始まります。お山の花も例年より10日くらい早まりそう?50代以降の事故が多いことから、生涯登山を目指すなら登山に必要な筋肉を鍛える『山筋ゴーゴー体操』の本が紹介された。1冊200円 (DVDが付いたものもあり)1日15分お手軽ですが、まじめに行うとけっこうキツイ?一度体験したいものです。
2月の行事報告
吉野山・・・天気は良かったが、放射冷却で冷え込んだ。途中見事なミズナラやブナの木が見られ、詳しい会員さんより樹木の雌雄説明を受けながらの登山となった。
古部丸山・・・今年から林道の除雪をしないと聞いていたが、雪が少なくなんとか入ることができた。今まで登っていたルートはやぶ漕ぎが煩わしいのと、枝を折ってしまうため、今回は東側の尾根を登りC451付近から前山へ向かうルートで登頂。
焼木尻岳・・・穏やかな春めいた日差しの登山日和。頂上から双耳峰の北ピークへ、そこから本峰を振り返ると例年通り巨大な雪庇が見られた。(危険!)昼食時、擦りつけられた毛の残る枝を見つけ、熊の毛かと思ったが『山姥の髪の毛』と言う面白い名前のキノコだった。
紋別岳・・・クマゲラの姿と鳴き声に感動し「雪まくり」(風により、地面に積もった雪がシート状にまくりあげられ、絨毯を巻いたような形状が作られる。)に春を感じる登山となった。

3月の行事予定
設計山 熊泊山 鹿部丸山 横津岳
学習会
山岳会の始まりと現在の動向について
2月の行事報告
吉野山・・・天気は良かったが、放射冷却で冷え込んだ。途中見事なミズナラやブナの木が見られ、詳しい会員さんより樹木の雌雄説明を受けながらの登山となった。
古部丸山・・・今年から林道の除雪をしないと聞いていたが、雪が少なくなんとか入ることができた。今まで登っていたルートはやぶ漕ぎが煩わしいのと、枝を折ってしまうため、今回は東側の尾根を登りC451付近から前山へ向かうルートで登頂。
焼木尻岳・・・穏やかな春めいた日差しの登山日和。頂上から双耳峰の北ピークへ、そこから本峰を振り返ると例年通り巨大な雪庇が見られた。(危険!)昼食時、擦りつけられた毛の残る枝を見つけ、熊の毛かと思ったが『山姥の髪の毛』と言う面白い名前のキノコだった。
紋別岳・・・クマゲラの姿と鳴き声に感動し「雪まくり」(風により、地面に積もった雪がシート状にまくりあげられ、絨毯を巻いたような形状が作られる。)に春を感じる登山となった。

3月の行事予定
設計山 熊泊山 鹿部丸山 横津岳
学習会
山岳会の始まりと現在の動向について