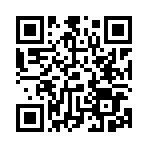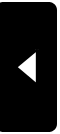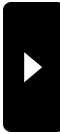2019年08月08日
8月7日(水) 8月例会
気温も湿度も高く、雨が降るわけでもなく、どんよりとしたうっとうしい天気の7月でした。それでも山行は何とか計画通り実施できました。まだ暑い日が夜も続きそうですが、本日の例会、会場にクーラーが入っていてとても快適!
7月の行事報告
7月7日(日)知内丸山
登山口に向かう途中、車のワイパーをつけるほどの雨だったが、登山開始時には止んだ。登りは途中の「八面樹」に気が付かないほどの霧だった。登山終了後、登山口にある小学校跡の小さな池のスイレンがきれいに咲いていた。
7月14日(日)狩場山
小雨が降り天気は良くなかったが、気温が低かったため楽に登ることができた。ただ、登山道が粘土質の泥で滑り、泥だらけ。
7月20日(土)石狩岳
登山開始から最後まで合羽を脱げなかった。花は期待していなかったが、思いがけなく、頂上近くにお花畑が広がっていた。
7月21日(日)横津岳~烏帽子岳・袴腰岳
久しぶりに横津の頂上付近に行ったが、手前と裏の方にトウゲブキが沢山咲いていて圧巻。歩いている途中雲海の上に出て、きれいだった。
7月28日(日)徳舜瞥山~ホロホロ山
岩の多い山で9合目まで花もあまりなく長く感じた。その上からは花が多く見られ楽しい気分で登ることができた。水場の上の方で遅くまで雪が残っていたためか、涼しい風が吹いてくる穴?がありほっと一息。
8月4日(日)袴腰岳(新中野ダムコース)
ちょうど笹狩りが終わった後で、とても歩きやすい登山道になっていた。第2登山口から登った。熊がいると聞いていたが、今回は熊の感じはしなかった。時期的にアブがうるさい。
8月の行事予定
余市岳 駒ヶ岳 尾札部川川歩き ピリカ丸山 大千軒岳
学習会 『地形図の見方』 1回目
模型を上から見て紙の上に等高線を書いてみました。地図を見てお山の凸凹を思い浮かべる学習です。(下の絵は例なのでお山と等高線はあっていません。)

7月の行事報告
7月7日(日)知内丸山
登山口に向かう途中、車のワイパーをつけるほどの雨だったが、登山開始時には止んだ。登りは途中の「八面樹」に気が付かないほどの霧だった。登山終了後、登山口にある小学校跡の小さな池のスイレンがきれいに咲いていた。
7月14日(日)狩場山
小雨が降り天気は良くなかったが、気温が低かったため楽に登ることができた。ただ、登山道が粘土質の泥で滑り、泥だらけ。
7月20日(土)石狩岳
登山開始から最後まで合羽を脱げなかった。花は期待していなかったが、思いがけなく、頂上近くにお花畑が広がっていた。
7月21日(日)横津岳~烏帽子岳・袴腰岳
久しぶりに横津の頂上付近に行ったが、手前と裏の方にトウゲブキが沢山咲いていて圧巻。歩いている途中雲海の上に出て、きれいだった。
7月28日(日)徳舜瞥山~ホロホロ山
岩の多い山で9合目まで花もあまりなく長く感じた。その上からは花が多く見られ楽しい気分で登ることができた。水場の上の方で遅くまで雪が残っていたためか、涼しい風が吹いてくる穴?がありほっと一息。
8月4日(日)袴腰岳(新中野ダムコース)
ちょうど笹狩りが終わった後で、とても歩きやすい登山道になっていた。第2登山口から登った。熊がいると聞いていたが、今回は熊の感じはしなかった。時期的にアブがうるさい。
8月の行事予定
余市岳 駒ヶ岳 尾札部川川歩き ピリカ丸山 大千軒岳
学習会 『地形図の見方』 1回目
模型を上から見て紙の上に等高線を書いてみました。地図を見てお山の凸凹を思い浮かべる学習です。(下の絵は例なのでお山と等高線はあっていません。)

2019年08月06日
8月4日 袴腰岳新中野ダムルート
今月最初の山行は袴腰岳新中野ダムルート。当会では2014年9月7日に第2登山口から登っている。昨年も7月8日に予定はしていたものの雨天で中止になった。現在第1登山口は入口も見えないほどの藪状態だったので,渡島総合振興局東部森林室の笹刈りがちょうど済んだ第2登山口から登ることにした。参加者13名。天気予報は良かったが,熱中症が心配されるほどの暑さ。なるべく涼しいうちに登ろうと考え集合時間を早くしていてよかった。8時には歩き始めることができた。
笹刈りが済んだ快適な道を行く。

何箇所か倒木があり,迂回した。

8時半,C680あたりで休憩。

C795あたりのきれいな登山道と三角山。


もう少し登ってC830あたりから見た雁皮山・庄司山とヨツバヒヨドリ。



9時15分三角山到着。少し休憩。

C1000あたりで頂上が見えた。

さらに登ると函館市街地と函館山がうっすらと見えて来る。頂上への最後の登りの前にひとしきり展望を楽しむ。虻も写った。



頂上近くの登りでやっと花が賑やかになった。オトギリソウ・アキノキリンソウ・ホツツジ。



10時半に頂上到着。早い昼食にする。その後全体写真を撮って11時前に下山開始。頂上からの展望は三角山の向うに雁皮山。


下山途中にツルリンドウとシュロソウが見られた。


予定よりずいぶん早く12時40分には下山した。駐車スペースの脇でOさんがタケシマランの実を見つけた。

装備を解いてダム公園駐車場まで戻り,改めて解散した。頂上での休憩を除くと4時間強の登山だった。病み上がりの私にはちょっときつかったが,みなさんは大いに夏山を楽しんだようだ。
笹刈りが済んだ快適な道を行く。

何箇所か倒木があり,迂回した。

8時半,C680あたりで休憩。

C795あたりのきれいな登山道と三角山。


もう少し登ってC830あたりから見た雁皮山・庄司山とヨツバヒヨドリ。



9時15分三角山到着。少し休憩。

C1000あたりで頂上が見えた。

さらに登ると函館市街地と函館山がうっすらと見えて来る。頂上への最後の登りの前にひとしきり展望を楽しむ。虻も写った。



頂上近くの登りでやっと花が賑やかになった。オトギリソウ・アキノキリンソウ・ホツツジ。



10時半に頂上到着。早い昼食にする。その後全体写真を撮って11時前に下山開始。頂上からの展望は三角山の向うに雁皮山。


下山途中にツルリンドウとシュロソウが見られた。


予定よりずいぶん早く12時40分には下山した。駐車スペースの脇でOさんがタケシマランの実を見つけた。

装備を解いてダム公園駐車場まで戻り,改めて解散した。頂上での休憩を除くと4時間強の登山だった。病み上がりの私にはちょっときつかったが,みなさんは大いに夏山を楽しんだようだ。
2019年07月31日
7月28日 徳舜瞥山~ホロホロ山
7月最後の山行は徳舜瞥山~ホロホロ山。前回は2年前の6月7日でほぼ2か月早かった。その時は残雪もあり,シラネアオイも見られたが,今回は真夏の登山となり,花もがらりと入れ替わっていた。天気は良かったが,水蒸気のせいか大気がぼんやりとしていて展望はあまり良くなかった。9時過ぎに登山口到着。すでにかなりの登山者の車があったが,駐車場は広いので5台でも楽に停めることができた。この日の参加者は12名。

9時23分登山開始。すぐ5合目の標識があり,意味が分からないが,何となくうれしい。入山届を書き,再出発。

まだ涼しい林の中を歩く。

夏になったばかりなのにアキノキリンソウ。

ゴゼンタチバナとツレサギソウ。


11時前に7合目を過ぎた。

空が近くなって来て,日差しが痛い。

だんだん日差しがきつくなる。見るのは足元ばかり。

やっと9合目の見晴台。見晴台からは羊蹄も見えず。


この辺りから急に花が増えて来た。ヨツバシオガマ・オトギリソウ・ウメバチソウ・チシマフウロ。




11時45分徳舜瞥山到着。すでに2グループが食事をしていた。われわれもツリガネニンジン(?)を見ながら昼食とする。展望は写真の通り。



食後全体写真。


12時20分ホロホロ山を目指す。途中徳舜瞥山を振り返り,きつい登り返しを覚悟する。

ホロホロ山頂上ももう少し。

12時54分ホロホロ山到着。少しくつろぐ。

ホロホロ山の北尾根はきれいに見えるが,白老岳方面はぼんやりしている。

ホロホロ山で全体写真。


13時ホロホロ山下山開始。13時40分には全員徳舜瞥山に戻った。


10分ほど休んで13時52分徳舜瞥山下山開始。15時52分5合目到着。Fさんが鐘を鳴らし,下山終了。

帰り支度の後,挨拶を済ませて車毎に解散した。私が函館に帰宅したのは午後8時半でした。途中蟠渓の温泉で汗を流し,壮瞥町のサクランボをお土産にできた。

9時23分登山開始。すぐ5合目の標識があり,意味が分からないが,何となくうれしい。入山届を書き,再出発。

まだ涼しい林の中を歩く。

夏になったばかりなのにアキノキリンソウ。

ゴゼンタチバナとツレサギソウ。


11時前に7合目を過ぎた。

空が近くなって来て,日差しが痛い。

だんだん日差しがきつくなる。見るのは足元ばかり。

やっと9合目の見晴台。見晴台からは羊蹄も見えず。


この辺りから急に花が増えて来た。ヨツバシオガマ・オトギリソウ・ウメバチソウ・チシマフウロ。




11時45分徳舜瞥山到着。すでに2グループが食事をしていた。われわれもツリガネニンジン(?)を見ながら昼食とする。展望は写真の通り。



食後全体写真。


12時20分ホロホロ山を目指す。途中徳舜瞥山を振り返り,きつい登り返しを覚悟する。

ホロホロ山頂上ももう少し。

12時54分ホロホロ山到着。少しくつろぐ。

ホロホロ山の北尾根はきれいに見えるが,白老岳方面はぼんやりしている。

ホロホロ山で全体写真。


13時ホロホロ山下山開始。13時40分には全員徳舜瞥山に戻った。


10分ほど休んで13時52分徳舜瞥山下山開始。15時52分5合目到着。Fさんが鐘を鳴らし,下山終了。

帰り支度の後,挨拶を済ませて車毎に解散した。私が函館に帰宅したのは午後8時半でした。途中蟠渓の温泉で汗を流し,壮瞥町のサクランボをお土産にできた。
2019年07月22日
7月21日 横津岳~袴腰岳
7月の自然部山行は大雪ツアーの「石狩岳」と重なり,函館「居残り」組で夏の横津岳~袴腰岳を楽しむことになった。天気予報は曇り時々晴れだったが,横津岳には雲が掛かっていた。あの雲の上には青空が広がっているのを期待した。総勢21名。以下Yさんの写真に基づき報告する。
登ってみると雲の上は期待通りの天気でトウゲブキやエゾカンゾウも雲海を背景に撮れた。


自然部らしく,ゆっくり花を見る。

思わず万歳をしたくなる?

頂上ドーム前で全体写真。

少し下りて雲井沼の静かなたたずまい。

烏帽子岳へ向かう途中からドームを振り返る。

湿原あたりでまたゆっくり観察。

烏帽子岳到着。トウゲブキが満開。


袴腰岳へ向かう組と烏帽子岳昼寝組とが別れ,烏帽子岳から袴腰岳組を写す。

烏帽子岳昼寝組の全体写真。

最後にオトギリソウ・ノハナショウブ・モウセンゴケとその花。

山の上は極楽だったようですね。私も行きたかった(:_;)。
登ってみると雲の上は期待通りの天気でトウゲブキやエゾカンゾウも雲海を背景に撮れた。
自然部らしく,ゆっくり花を見る。
思わず万歳をしたくなる?
頂上ドーム前で全体写真。
少し下りて雲井沼の静かなたたずまい。
烏帽子岳へ向かう途中からドームを振り返る。
湿原あたりでまたゆっくり観察。
烏帽子岳到着。トウゲブキが満開。
袴腰岳へ向かう組と烏帽子岳昼寝組とが別れ,烏帽子岳から袴腰岳組を写す。
烏帽子岳昼寝組の全体写真。
最後にオトギリソウ・ノハナショウブ・モウセンゴケとその花。

山の上は極楽だったようですね。私も行きたかった(:_;)。
2019年07月21日
7月20日(土) 石狩岳(大雪ツアー)
7月三回目の会山行は、大雪ツアーとして東大雪山系の主峰・石狩岳(1,966m)。日本海へそそぐ石狩川と、太平洋に流れる音更川(十勝川支流)の源流に聳える。最短だが急登が続くシュナイダーコース(別名「熊ころがし」)を利用して往復した。参加は8名。
前泊した糠平湖畔のホテルを4時30分、車3台で出発。従来の音更川支線林道が通行止めのため、国道273号線三国峠手前の標高783m地点から西に入るシンノスケ迂回林道を利用して、音更川本流と二十一ノ沢の出合にある広い駐車場(標高803m)に乗り入れる。
小雨が降る中、駐車場で雨具上下を身に付けて準備を整え、5時50分に出発。
ちなみにコース名「シュナイダー」の由来はオーストリアの登山家やスキー術創始者の説、北海道夏山ガイドでは「野球用語のスライダー(ピッチャーが投げる球種)をもじったもの」との説がある。登ってみた感想として、尾根がスキージャンプ台の助走路のような形をしているところからスライダー(滑るもの)と付けられ、これが訛ったのではないかと勝手に想像してみる。登山口から頂上までの標高差は1,163m。

尾根の取り付き地点まで、始めは二十一ノ沢左岸に付けられた緩い傾斜の樹林帯笹原道を辿る。

C870付近で体温調整のため休憩。雨はほぼ止んだが、木から落ちる水滴や濡れた笹などのため、雨具は外せない。内側衣服のファスナーを空けたり、腕まくりをしたりして体温を逃す。

登山口から約1.4km、C900付近で二十一ノ沢を渡る。心配した水量は少なかったので、楽に渡渉できた。

沢右岸の樹林帯に、古い切り株の上に根を張った若い針葉樹があった。生命の逞しさを感じる。

登山口から約1.9km、C950付近で尾根に上がる斜面に取り付く。登山道は尾根の稜線に向かってジグザグを切りながら上がるが、それでも傾斜はかなり急だ。

この斜面で、クルマユリの花、カエデ属の実、白色が目立つマタタビの葉が見られた。



C1090付近で尾根の稜線に達すると、傾斜がいったん弱まる。細い尾根を辿っていくと、所々にハクサンシャクナゲの花が残っていた。

尾根の傾斜は次第にきつくなり、C1400付近から岩場が多く現れてくる。両手も動員して慎重に登る。

C1500付近にある、「かくれんぼ岩」と名付けられた大きな岩。このあたりから再び雨が降り出し、カメラのレンズに水滴が付いたため、これ以降の画像がにじんでしまった…m(_ _)m。

周りはすっかり這松帯となり、雨で滑りやすくなった露岩帯を慎重に。

霧の中、石狩岳・音更山の分岐がある主稜線に近づいてきた。

C1770付近の分岐に飛び出すと、今年初めて目にするコマクサの群落が出迎えてくれた。


鮮やかな赤色のエゾツツジも…。

見通しが効かない中、分岐から石狩岳頂上に向かって出発。

C1800付近から豊かなお花畑となり、多くの高山植物が目に入ってきた。ヨツバシオガマ(左上)、チシマフウロ(右上)、イワブクロ(左下)、シナノキンバイ(右下)。

チングルマの実(左上)、チングルマの花(右上)、アオノツガザクラ(左下)、イワヒゲ(右下)。

さらに、コエゾツガザクラ(左)、アキノキリンソウ(右)。

11時20分、頂上に到着(登り5時間30分)。視界20~30メートルで雄大なパノラマは望むべくもなかったが、風は弱く気温もそこそこ暖かかったので、ゆったりと昼食を摂ることができた。恒例の全体写真を撮って、11時55分に下山開始。


急で滑りやすい岩場や泥道を、ゆっくりと慎重に下りた。渡渉地点の沢で登山靴、スパッツ、雨具ズボンの裾、ポールなどを沢水で洗い、身を清めて(?)から「天狗神弁慶霊」の祠の前を通り、16時10分、駐車場に到着(下り4時間15分)。
展望こそ得られなかったが気温は割合に高くて風が弱く、午後は局地的に雷の可能性もあったが(雷鳴が1回聞こえたという複数メンバーも)雨風や雷が強くなることもなく、ラッキーであった。沢山の高山植物にも逢えて、良い山行になった。
糠平湖畔のホテルに戻り、温泉で汗を流してから楽しく夕食をいただいた。その後も有志が一部屋に集まってビールなどを飲みながら歓談しつつ、夜が更けていった。
前泊した糠平湖畔のホテルを4時30分、車3台で出発。従来の音更川支線林道が通行止めのため、国道273号線三国峠手前の標高783m地点から西に入るシンノスケ迂回林道を利用して、音更川本流と二十一ノ沢の出合にある広い駐車場(標高803m)に乗り入れる。
小雨が降る中、駐車場で雨具上下を身に付けて準備を整え、5時50分に出発。
ちなみにコース名「シュナイダー」の由来はオーストリアの登山家やスキー術創始者の説、北海道夏山ガイドでは「野球用語のスライダー(ピッチャーが投げる球種)をもじったもの」との説がある。登ってみた感想として、尾根がスキージャンプ台の助走路のような形をしているところからスライダー(滑るもの)と付けられ、これが訛ったのではないかと勝手に想像してみる。登山口から頂上までの標高差は1,163m。

尾根の取り付き地点まで、始めは二十一ノ沢左岸に付けられた緩い傾斜の樹林帯笹原道を辿る。

C870付近で体温調整のため休憩。雨はほぼ止んだが、木から落ちる水滴や濡れた笹などのため、雨具は外せない。内側衣服のファスナーを空けたり、腕まくりをしたりして体温を逃す。

登山口から約1.4km、C900付近で二十一ノ沢を渡る。心配した水量は少なかったので、楽に渡渉できた。

沢右岸の樹林帯に、古い切り株の上に根を張った若い針葉樹があった。生命の逞しさを感じる。

登山口から約1.9km、C950付近で尾根に上がる斜面に取り付く。登山道は尾根の稜線に向かってジグザグを切りながら上がるが、それでも傾斜はかなり急だ。

この斜面で、クルマユリの花、カエデ属の実、白色が目立つマタタビの葉が見られた。



C1090付近で尾根の稜線に達すると、傾斜がいったん弱まる。細い尾根を辿っていくと、所々にハクサンシャクナゲの花が残っていた。

尾根の傾斜は次第にきつくなり、C1400付近から岩場が多く現れてくる。両手も動員して慎重に登る。

C1500付近にある、「かくれんぼ岩」と名付けられた大きな岩。このあたりから再び雨が降り出し、カメラのレンズに水滴が付いたため、これ以降の画像がにじんでしまった…m(_ _)m。

周りはすっかり這松帯となり、雨で滑りやすくなった露岩帯を慎重に。

霧の中、石狩岳・音更山の分岐がある主稜線に近づいてきた。

C1770付近の分岐に飛び出すと、今年初めて目にするコマクサの群落が出迎えてくれた。


鮮やかな赤色のエゾツツジも…。

見通しが効かない中、分岐から石狩岳頂上に向かって出発。

C1800付近から豊かなお花畑となり、多くの高山植物が目に入ってきた。ヨツバシオガマ(左上)、チシマフウロ(右上)、イワブクロ(左下)、シナノキンバイ(右下)。

チングルマの実(左上)、チングルマの花(右上)、アオノツガザクラ(左下)、イワヒゲ(右下)。

さらに、コエゾツガザクラ(左)、アキノキリンソウ(右)。

11時20分、頂上に到着(登り5時間30分)。視界20~30メートルで雄大なパノラマは望むべくもなかったが、風は弱く気温もそこそこ暖かかったので、ゆったりと昼食を摂ることができた。恒例の全体写真を撮って、11時55分に下山開始。


急で滑りやすい岩場や泥道を、ゆっくりと慎重に下りた。渡渉地点の沢で登山靴、スパッツ、雨具ズボンの裾、ポールなどを沢水で洗い、身を清めて(?)から「天狗神弁慶霊」の祠の前を通り、16時10分、駐車場に到着(下り4時間15分)。
展望こそ得られなかったが気温は割合に高くて風が弱く、午後は局地的に雷の可能性もあったが(雷鳴が1回聞こえたという複数メンバーも)雨風や雷が強くなることもなく、ラッキーであった。沢山の高山植物にも逢えて、良い山行になった。
糠平湖畔のホテルに戻り、温泉で汗を流してから楽しく夕食をいただいた。その後も有志が一部屋に集まってビールなどを飲みながら歓談しつつ、夜が更けていった。